投稿者: nichinaekenbyo-master
広報誌なんぷう【第9号】
広報誌なんぷう【第8号】
広報誌なんぷう【第7号】
広報誌なんぷう【第6号】
平成17年度 第4章 職員の状況・資料等
5. 学会認定施設状況(2006年3月31日現在)
| 診療科名 | 学会名 | 認定名称 | 施設認定日 |
|---|---|---|---|
| 内科 | 日本循環器学会 | 循環器専門医研修施設 | 2001.3.1 |
| 日本肥満学会 | 肥満症専門病院認定施設 | 2004.9.28 | |
| 日本透析医学会 | 宮崎大学医学部附属病院教育関連施設 | 2004.11.12 | |
| 小児科 | 日本小児科学会 | 認定医研修施設(関連) | |
| 外科 | 日本外科学会 | 認定医制度関連施設 | 1998.1.1 |
| 日本呼吸器外科学会 | 専門医制度関連施設 | 1999.1.1 | |
| 日本胸部外科学会 | 認定医認定制度関連施設 | 1999.1.1 | |
| 日本消化器外科学会 | 認定医認定制度関連施設 | 1999.1.1 | |
| 日本呼吸器内視鏡学会 | 認定施設 | 2002.1.1 | |
| 整形外科 | 日本整形外科学会 | 認定研修施設 | |
| 脳神経外科 | 日本脳神経外科学会 | 専門医認定指定訓練場所(関連) | 1999.1.1 |
| 皮膚科 | 日本皮膚科学会 | 専門医研修施設 | 1999.4.1 |
| 泌尿器科 | 日本泌尿器科学会 | 専門医教育施設 | 1986.4.1 |
| 産婦人科 | 日本産科婦人科学会 | 卒後研修指導施設 | |
| 日本母性保護医協会 | 母体保護法指定医師研修機関 | ||
| 日本周産期・新生児医学会 | 周産期新生児専門医の暫定研修施設 | 2004.4.1 | |
| 眼科 | 日本眼科学会 | 専門医制度研修施設 | 1985.10.1 |
| 耳鼻咽喉科 | 日本耳鼻咽喉科学会 | 専門医研修施設 | 1999.4.1 |
| 放射線科 | 日本医学放射線学会 | 専門医修練協力機関(放射線診断学、核医学、放射線治療学) | 2000.12.20 |
| 麻酔科 | 日本麻酔学会 | 麻酔指導病院 | 1993.6.18 |
| 臨床検査科 | 日本病理学会 | 登録施設 | 2005.4.1 |
| 日本臨床細胞学会 | 細胞診認定施設 | 2003.5.30 |
6. 学会評議員資格状況(2005年4月~2006年3月の在籍者)
| 診療科名 | 医師等氏名 | 学会名 | 資格取得日 |
|---|---|---|---|
| 内科 | 上田 正人 | 日本動脈硬化学会 | |
| 内科 | 上田 正人 | 日本肥満学会 | |
| 内科 | 上田 正人 | 日本過酸化脂質学会 | |
| 内科 | 上田 正人 | 日本未病学会 | |
| 外科 | 柴田 紘一郎 | 日本胸部外科学会 | |
| 外科 | 柴田 紘一郎 | 日本呼吸器内視鏡学会 | |
| 外科 | 柴田 紘一郎 | 日本呼吸器学会 | |
| 外科 | 柴田 紘一郎 | 日本呼吸器外科学会 | |
| 外科 | 柴田 紘一郎 | 日本肺癌学会 | |
| 外科 | 柴田 紘一郎 | 日本臨床外科学会 | |
| 外科 | 柴田 紘一郎 | 日本内視鏡外科学会 | |
| 整形外科 | 長鶴 義隆 | 日本小児整形外科学会 | 1990.11.16 |
| 整形外科 | 長鶴 義隆 | 日本股関節学会 | 1990.10.30 |
| 泌尿器科 | 新川 徹 | 日本泌尿器科学会 | 1990.6.15 |
| 麻酔科 | 長田 直人 | 日本集中治療医学会 | |
| 麻酔科 | 長田 直人 | 日本集中治療医学会九州地方会 | |
| 麻酔科 | 長田 直人 | 日本救急医学会九州地方会 | |
| 臨床検査科 | 木佐貫 篤 | 日本病理学会 | 2000.4.12 |
| 臨床検査科 | 木佐貫 篤 | 日本医療マネジメント学会 | 2005.6 |
7. 宮崎大学医学部学生教育
| 診療科名 | 医師等氏名 | 宮崎大学医学部称号名 | 発令日 |
|---|---|---|---|
| 内科 | 上田 正人 | 臨床教授 | 2005.4.13 |
| 内科 | 石崎 淳三 | 臨床教授 | 2005.4.13 |
| 外科 | 柴田 紘一郎 | 臨床教授 | 2005.4.13 |
| 外科 | 峯 一彦 | 臨床教授 | 2005.4.13 |
| 整形外科 | 長鶴 義隆 | 臨床教授 | 2005.4.13 |
| 麻酔科 | 長田 直人 | 臨床教授 | 2005.4.13 |
| 臨床検査科 | 木佐貫 篤 | 臨床助教授 | 2005.4.13 |
8. 県立日南病院に関する報道
| 年月日 | 掲載紙名 | 内容等 |
|---|---|---|
| 17.8.2 | 宮崎日日新聞 | 心癒やす歌声響く(勢井さん県病院で演奏会) |
| 17.9.7 | 宮崎日日新聞 | 女性専用外来「わかば」開設 県立日南病院 |
| 17.9.14 | 宮崎日日新聞 | まちかど (県立日南病院職員黒木香織) |
| 17.9.24 | 朝日新聞 | 女性専用外来来月から開設 県立日南病院 |
| 17.9.30 | 朝日新聞 | 県立日南病院でバイキング |
| 17.10.1 | 宮崎日日新聞 | 入院食に「選ぶ」楽しさを 県立日南病院 初の昼食バイキング実施 |
| 17.10.21 | 読売新聞 | 日南病院に女性外来(きょうオ-プン) |
| 17.10.23 | 宮崎日日新聞 | 女性専用外来スタ-ト(県内2番目 更年期、不調相談も) 県立日南病院 |
| 17.10.28 | 宮崎日日新聞 | 岬太郎(日南病院女性専用外来関係コラム) |
| 17.11.30 | 宮崎日日新聞 | 検診や試食が好評(県立日南病院祭にぎわう) |
| 17.12.4 | 宮崎日日新聞 | 素直な気持ち 書き記し展示(患者さんの気持ち・看護師さんの 気持ち・お医者さんの気持ち展とこどもスケッチ展) |
| 17.12.13 | 宮崎日日新聞 | 県立日南病院 クリスマス演奏会 |
| 17.12.28 | 宮崎日日新聞 | 初動態勢を確認 県立日南病院 住民も参加し消防訓練 |
| 18.1.8 | 宮崎日日新聞 | 七福神の宝船 患者に「元気」 |
| 18.1.10 | 宮崎日日新聞 | まちかど(県立日南病院副総看護師長 山崎美鈴) |
| 18.1.11 | 読売新聞 | 七福神と一諸に「元気」運ぶ宝船 |
| 18. 1.20 | 宮崎日日新聞 | 看護師長アドバイス 県立日南病院 「健康相談室」を設置 |
| 18.2.7 | 宮崎日日新聞 | みにミニみに 縁起物は重宝 県立日南病院の模型「宝船」がキッチンバレ-ヌへ |
| 18.2.19 | 宮崎日日新聞 | みにミニみに 赤ヘルパワ-で患者に元気 県立日南病院に広島全選手のサイン展示 |
| 18.3.11 | 宮崎日日新聞 | (岬太郎) 県立日南病院の柴田紘一朗院長が定年退職する。 |
テレビ放映
日南CATV
- 平成17 年10月13日~14日
- 「県立日南病院こどもスケッチ大会」開催
9. 医療訴訟の状況
平成17年度は、該当なし。
平成17年度 第3章 研究業績
1. 論文・誌上発表、学会・研究会発表及び講演
(1) 各診療科別発表数
| 論文・誌上発表 | 学会・研究会発表 | 講演 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 内科 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外科 | 4 | 17 | 4 | 2 |
| 整形外科 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 脳神経外科 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 皮膚科 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 泌尿器科 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 産婦人科 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 眼科 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 放射線科 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 麻酔科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 臨床検査科 | 6 | 14 | 0 | 1 |
| 薬剤科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護科 | 1 | 16 | 8 | 0 |
| 地域医療連携室 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 計 | 19 | 72 | 29 | 4 |
(院内向け発表はのぞく)
※論文・誌上発表、学会研究会の研究業績の収載基準
医師関係の論文、誌上発表、学会、研究会の研究業績の収載に当たっては以下の基準にて記載した。
- 年報の期間(平成17年4月~平成18年3月)に本院に在籍していた医師の氏名が記載されているもの。従って、研究業績が本院で行われたものとは限らない。
- 講演は、本院に在籍中の発表分とした。
- 複数科での業績は各科毎に掲載した。従って、業績が重複しているものもあり、総計も重複している。
- その他には、学術論文以外の誌上発表などを含んでいる。
- リハビリテーション科は整形外科にまとめて掲載した。
(2) 各診療科業績一覧
【内科・神経内科】
(原著、著書、誌上発表)
- 胸水の鑑別疾患に寄生虫も考慮する。
平塚雄聡
「呼吸器診療のコツと落とし穴①呼吸器感染症」工藤翔二編 pp112,中山書店,2005 - 興味ある画像所見の変化を呈したウエステルマン肺吸虫症の1例。
今津善史、芦谷淳一、今井光一、柳重久、佐野ありさ、床島眞紀、中里雅光
日呼吸会誌 43:771-774,2005
(学会、研究会発表)
- 肺抗酸菌症における血漿グレリン濃度の検討。
有村保次、京樂由佳、飯干宏俊、平塚雄聡、伊井敏彦、隈本健司、芦谷淳一、中里雅光
第45回日本呼吸器学会総会 2005年4月16日,千葉市 - 咽頭結膜熱にウイルス性肺炎を合併した1症例。
深江裕子、渡邊玲子、窪山美穂、高木信雄、福留慶一、平山直輝、松尾剛史、石川正
第269回日本内科学会九州地方会 2005年5月21日,福岡市 - 人工呼吸管理にて救命し得たクラミジア肺炎を合併したじん肺症の一例-シベレスタットナトリウムの使用経験-。
今津善史、平塚雄聡、西園隆三、深江裕子、石原旅人、藤浦芳丈、生島一平、石崎淳三、上田正人、長田直人
急性肺障害の病態と治療研究会 2005年6月23日,日南市 - 血小板増加、溶血、好中球アルカリフォスファターゼ活性低下を認めた、MDS/MPDと思われる1例。
石崎淳三、上田正人
第67回日本血液学会、第47回日本臨床血液学会合同総会 2005年9月18日,横浜市 - Buci11amineによる薬剤性肺炎の一例。
今津善史、平塚雄聡、林英里香、深江裕子、石原旅人、藤浦芳丈、生島一平、石崎淳三、上田正人、木佐貫篤
第272回日本内科学会九州地方会 2006年1月28日,福岡市 - 血液透析導入前に心嚢液及び胸水を呈し抗結核剤が著効した1症例。
深江裕子、林英里香、今津善史、平塚雄聡、、石原旅人、藤浦芳丈、生島一平、石崎淳三、上田正人
第272回日本内科学会九州地方会 2006年1月28日,福岡市
(講演)
- 間違いだらけの心電図の勉強法~不整脈編。
藤浦芳丈
第8回県立日南医療連携セミナー 2005年5月24日,日南市 - 高齢者の気管支喘息治療。
平塚雄聡
日医生涯教育協力講座/慢性呼吸器疾患講座セミナー 2006年3月4日,宮崎市
【外科】
(原著、著書、誌上発表)
- 止血目的で放射線治療を施行した進行胃癌の2例。
清水勅君、柴徹、峯一彦、柴田紘一郎、木佐貫篤、吉澤大、井上龍二、黒木和男
臨床放射線50:793-797,2005 - 進行胃癌と連続して存在した巨大嚢胞性腫瘍の1例。
清水勅君、柴徹、小谷幸生、峯一彦、柴田紘一郎、桂木真司、春山康久、木佐貫篤
臨床放射線50:1057-1062,2005 - 遭伝子解析を行った胃gastrointestinal stromal tumor (GIST)の1例。
山口由美、松田俊太郎、峯一彦、河野文彰、種子田優司、市成秀樹、柴田紘一郎
宮崎県医師会医学会誌 30:39-42,2006 - 大腿ヘルニア根治術後のメッシュ感染の1例。
松田俊太郎、峯一彦、河野文彰、小谷幸生、市成秀樹、柴田紘一郎
臨床外科 61:105-107,2006
(学会、研究会発表)
- 急性虫垂炎を発症して発見された虫垂開口部盲腸癌の2例。
松田俊太郎、河野文彰、小谷幸生、市成秀樹、峯一彦、柴田紘一郎
第42回九州外科学会 2005年5月27日,熊本市 - 当科における自然気胸に対する胸腔鏡下手術の工夫;ポリグリコ-ル酸シートと自己血を用いた方法。
市成秀樹、峯一彦、小谷幸生、松田俊太郎、河野文彰、柴田紘一郎
第22回日本呼吸器外科学会総会 2005年6月3日,京都市 - 集中治療により救命し得た胆汁性腹膜炎の1例。
- 子宮広間膜ヘルニアの1手術例と本邦報告例の検討。
河野文彰、松田俊太郎、小谷幸生、市成秀樹、峯一彦、柴田紘一郎
第30回日本外科系連合学会 2005年6月24日,東京都 - 胃GISTの1例。
山口由美、河野文彰、松田俊太郎、小谷幸生、市成秀樹、峯一彦、柴田紘一郎
宮崎県外科医会夏期講演会 2005年8月5日,宮崎市 - 直腸吻合不全に対するヒストアクリルの使用経験。
大平洋明、河野文彰、松田俊太郎、小谷幸生、市成秀樹、峯一彦、柴田紘一郎
宮崎県外科医会夏期講演会 2005年8月5日,宮崎市 - 急性虫垂炎を伴う虫垂開口部盲腸癌の臨床病理学的検討。
松田俊太郎、河野文彰、種子田儀司、市成秀樹、峯一彦、柴田紘一郎
第26回宮崎救急医学会 2005年8月6日,宮崎市 - 当科における自然気胸に対する手術の工夫。
市成秀樹、峯一彦、種子田儀司、河野文彰、柴田紘一郎
第6回第2外科懇話会 2005年9月3日,宮崎市 - 直腸神経内分泌細胞癌の1治験例。
河野文彰、松田俊太郎、小谷幸生、市成秀樹、峯一彦、柴田紘一郎
第60回日本大腸肛門病学会総会 2005年9月30日,東京都 - 長期に観察し潰瘍性病変の1例。
松田俊太郎、河野文彰、小谷幸生、市成秀樹、峯一彦、柴田紘一郎、木佐貫篤
宮崎胃と腸懇話会 2005年9月30日,宮崎市 - 成人鼠径ヘルニア根治術パスにおいて鎮痛薬の定期内服が及ぼす効果。
阿比留知子、松田俊太郎、木佐井篤
第4回医療マネジメント学会九州山口連合大会 2005年10月29日,福岡市 - 急性虫垂炎を伴う虫垂関口部盲癌の臨床病理学的検討。
松田俊太郎、河野文彰、小谷幸生、市成秀樹、孝一彦、柴田紘一郎
第67回日本臨床外科学会総会 2005年11月9日,東京都 - 腺回転異常症を伴った胃癌の2手術症例。
河野文彰、峯一彦、市成秀樹、小谷事生、松田俊太郎、柴田紘一郎
第67回日本臨床外科学会総会 2005年11月11日,東京都 - 当科における呼吸器外科領域の手術の工夫。
市成秀樹、河野文彰、松田俊太郎、小谷幸生、峯一彦、柴田紘一郎
第17回宮崎呼吸器懇話会 2005年11月11日,宮崎市 - 当院における腹睦鑓下総胆管切石術の工夫。
松田俊太郎、峯一彦、河野文彰、種子田俵司、市成秀樹、柴田紘一郎
第80回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 2005年11月18日,熊本市 - 当科における胸腔鏡下自然気胸手術の工夫。
市成秀樹、河野文彰、松田俊太郎、小谷幸生、峯一彦、柴田紘一郎
第4回宮崎内視鏡外科研究会 2005年12月2日,宮崎市 - 腹腔鏡下総胆管切石術における20mmポートの有用性。
松田俊太郎、市成秀樹、河野文彰、小谷幸生、峯一彦、柴田紘一郎
第106回日本外科学会総会 2006年3月31日,東京都
(講演)
- 活き、意気と生きる。
柴田紘一郎
西岳中学校講演会 2005年7月3日,都城市 - 活き、意気と、粋に、よどみなく生きる。一志をもちつづける事の意味-。
柴田紘一郎
宮崎大宮高校いちいち会セミナー 2005年8月17日,宮崎市 - 肺癌の外科治療一黎明期よりEvidence BasedMedicineへ。
柴田紘一郎
宮崎大学医学部学生特別溝義(4年生)2005年9月26日,宮崎郡 - 胃瘻の構造について。
松田俊太郎
第10回県立日南医療連携セミナー 2006年3月10日,日南市
(その他)
- 依頼投稿:生と死の間の闘いを、ともに闘いたい。
柴田紘一郎
宮崎大宮高校弦月同窓会会報 2005年10月 - 書評:「41歳、僕は教師をやめて医者になりました」
柴田紘一郎
宮崎日々新開 2005年10月23日
【整形外科・リハビリテーション科】
(原著、著書、誌上発表)
- 上腕骨近位端骨折の保存的治療成績。
松岡知己、長鶴義隆、川野彰裕、中村嘉宏
宮崎整形外科懇話会論文集 第9号,2005
(学会、研究会発表)
- 脛骨プラトー骨折の治療成積。
松岡知己、長鶴義隆、川野彰裕、中村嘉宏
第50回宮崎整形外科懇話会 2005年6月25日,宮崎市 - 寛骨臼球状骨切り術 (SAO)の適応とその限界。
長鶴義隆、川野彰裕
第32回日本股関節学会シンポジウム 2005年11月7日,新潟市 - 先天性股関節亜脱臼に対する保存的治療の成績。- 乳児期から骨成長期終了時までの長期治療例の検討。-
川野彰裕、長鶴義隆
第16回日本小児整形外科学会 2005年11月18日,盛岡市 - 当科における大腿骨頭壊死の治療について。
桐谷力、長鶴義隆、松岡知己、川野彰裕
第51回宮崎整形外科食詰会 2005年12月17日,宮崎市
【脳神経外科】
(講演)
- 脳神経外科領域における血管内治療の役割一虚血性脳血管障害及びくも膜下出血を中心に-
米山匠
南那珂医師会生涯教育医学会 2005年11月4日,日南市
【皮膚科】
(学会、研究会発表)
- 薬剤過敏症症候群(DIHS)を疑った1例。
長嶺英宏、加嶋亜紀、菊池英維、留野朋子
第104回日本皮膚科学会宮崎地方会 2005年4月10日,宮崎市 - アミノフリード点滴漏れによる重症組織障害の1例。
加嶋亜紀、長嶺英宏
第104回日本皮膚科学会宮崎地方会 2005年4月10日,宮崎市 - 良性対称性脂肪腫症の1例-併発した頸部運動制限に対する手術治療例-。
持田耕介、帖佐宣昭、小田裕次郎、立山直、緒方克己、瀬戸山充
第104回日本皮膚科学会総会 2005年4月22日,横浜市 - 切除後8年目に再発し、診断確定したDermatofibrosarcoma protuberansの1例。
長嶺英宏、加嶋亜紀
第3回南九州地区合同皮膚外科地方会 2005年7月9日,宮崎市 - 初診から4年後に診断に至った全身性強皮 (limited cutaneous systemic sclerosis)
持田耕介、長嶺英宏
第106回日本皮膚科学会宮崎地方会 2005年12月4日,宮崎市 - 手術と保存的治療の狭間で。
長嶺英宏、持田耕介、加嶋亜紀
第106回日本皮膚科学会宮崎地方会 2005年12月4日,宮崎市
【泌尿器科】
(学会、研究会発表)
- DICを改善し得た尿管結石による膿腎症の一例。
高森大樹、新川徹、長田直人
日本泌尿器科学会第77回宮崎地方会 2006年1月14日、宮崎市
【産婦人科・NICU】
(原著、著書、誌上発表)
- 進行胃癌と連続して存在した巨大嚢胞性腫瘍の1例。
清水勅君、柴徹、小谷幸生、峯一彦、柴田紘一郎、桂木真司、春山康久、木佐貫篤
臨床放射線50:1057-1062,2005
(講 演)
- いのち健やか性教育研修会シンポジウム 今、性教育に求められているもの2005「宮崎の若者たちは今…アンケート調査より」。
春山康久
宮崎県医師会館 2005年5月28日,宮崎市 - 宮崎県学校・地域保健連携推進事業 性教育講演会「命の大切さ」。
春山康久
北郷中学校 2005年11月16日,北郷町 - 宮崎県学校・地域保健連携推進事業 性教育講演会「高校生を取り巻く性の問題」.
春山康久
県立福島高校 2005年11月22日,串間市 - 宮崎県学校・地域保健連携推進事業 性教育講演会「生命の大切さと死について」。
春山康久
榎原中学校 2005年12月21日,南郷町 - 命の大切さを考える講演会「死を通して生を考える」。
春山康久
吉野方小学校 2006年1月27日,日南市 - 日南市周産期医療協議会講演会「妊娠中の母体管理」。
春山康久
日南保健所 2006年2月15日,日南市 - いのち健やか性教育研修会(県南地区研修会)「性感染症について」。
春山康久
まなびや 2006年2月25日,日南市
【眼科】
(学会、研究会発表)
- 網膜中心静脈閉塞症に対するトリアムシノロンおよび組織プラスミノーゲン活性化因子併用療法。
福島慶美、齋藤真美
日本網膜硝子体学会 2005年12月3日,大阪市
【耳鼻咽喉科】
(学会、研究会発表)
- クリティカルパス展示:扁桃摘出術。
竹中美香
第7回医療マネジメント学会学術総会 2005年6月24-25日,福岡市 - 手術時手指消毒の有効な方法の基礎的検討~手洗い方法の改善に向けて~。
横尾明子、大嶋雅代、谷口陽子、木佐貫篤、津曲洋明、竹中美香
第7回医療マネジメント学会学術総会 2005年6月25日,福岡市 - 県立日南病院平成16年入院統計。
竹中美香、直野秀和
日耳鼻宮崎県地方部会学術講演会 2005年12月,宮崎市
【放射線科】
(原著、著書、誌上発表)
- 止血目的で放射線治療を施行した進行胃癌の2例。
清水勅君、柴徹、峯一彦、柴田紘一郎、木佐貫篤、吉澤大、井上龍二、黒木和男
臨床放射線50:793-797,2005 - 進行胃癌と連続して存在した巨大嚢胞性腫瘍の1例。
清水勅君、柴徹、小谷幸生、峯一彦、柴田紘一郎、桂木真司、春山康久、木佐貫篤
臨床放射線50:1057-1062,2005 - 4種類測定法による血清カルシウム測定試薬の基礎的検討。
鞍津輪優子、岩切尚子、藪押利香、籠正利、栗山儀明
宮臨技会誌86:9-12,2006
(学会、研究会発表)
- ESDについて。
山本雄一郎
第47回南那珂消化器カンフアレンス 2005年11月10日,宮崎市
(講 演)
- 胃癌検診と最近の話題。
山本雄一郎
平成17年度宮崎県医師会成人病検診従事者研修会 2005年12月3日,延岡市 - 胃癌検珍と最近の話題。
山本雄一郎
平成17年度宮崎県医師会成人病検診従事者研修会 2005年12月9日,宮崎市 - 胃癌検診と最近の話題。
山本雄一郎
平成17年度宮崎県医師会成人病検診従事者研修会 2005年12月10日,都城市
【麻酔科・ICU】
(原著、著書、誌上発表)
- 手術部とICU間の一足制は可能か。
長田直人、江川久子、田村隆二
日本集中治療医学会誌12:373-375,2005
(学会、研究会発表)
- 人工呼吸管理にて救命し得たクラミジア肺炎を合併したじん肺症の一例-シベレスタットナトリウムの使用経験-。
今津善史、平塚雄聡、西園隆三、深江裕子、石原旅人、藤浦芳丈、生島一平、石崎淳三、上田正人、長田直人
急性肺障害の病態と治療研究会 2005年6月23日,日南市 - DICを改善し得た尿管結石による膿腎症の一例。
高森大樹、新川徹、長田直人
日本泌尿器科学会第77回宮崎地方会 2006年1月14日、宮崎市
(講 演)
- 呼吸生理と人工呼吸器
長田直人
フクダ電子株式会社主催研修会 2005年8月6日,宮崎市 - 院内感染対策の最近の知見。
【臨床検査科】
(原著、著書、誌上発表)
- 止血目的で放射線治療を施行した進行胃癌の2例。
清水勅君、柴徹、峯一彦、柴田紘一郎、木佐貫篤、吉澤大、井上龍二、黒木和男
臨床放射線50:793-797,2005 - 乳腺腫瘤穿刺吸引細胞診の検討。
木佐貫篤、長友明彦、福田早織
日臨細胞九州会蕃36:133-137,2005 - 進行胃癌と連続して存在した巨大嚢胞性腫瘍の1例。
清水勅君、柴徹、小谷幸生、峯一彦、柴田紘一郎、境木真司、春山康久、木佐貫篤
臨床放射線50:1057-1062,2005
(学会、研究会発表)
- 頚部腫瘤生検捺印細胞診で判定困難だった胎児性癌の一例。
小牧誠、木佐貫篤
第46回日本臨床細胞学会春期大会(総会)2005年5月27日,福岡市 - 手術時手指消毒の有効な方法の基礎的検討~手洗い方法の改善に向けて小~。
横尾明子、大場雅代、谷口陽子、津曲洋明、木佐貫篤、竹中美香
第7回医療マネジメント学会学術総会 2005年6月25日,福岡市 - 乳腺腫瘤:Glycogen-rich clear cell carcinoma。
福田早織
平成17年度日本臨床細胞学会宮崎県支部第2回細胞診従事者研修会・症例検討会 2005年7月23日,宮崎市 - 長期に観察した潰瘍性病変の1例。
松田俊太郎、河野文彰、小谷幸生、市成秀樹、峯一彦、柴田紘一郎、木佐貫篤
宮崎胃と腸懇話会 2005年9月30日,宮崎市 - 成人鼠径ヘルニア根治術パスにおいて鎮痛薬の定期内服が及ぼす効果。
阿比留知子、松田俊太郎、木佐貫篤
第4回医療マネジメント学会九州山口連合大会 2005年10月29日,福岡市 - 新判定基準に基づく甲状腺穿刺吸引細胞診の検討。
福田早織、木佐貫篤
第44回日本臨床細胞学会秋期大会 2005年11月11-12日,奈良市 - 4種類測定法による血清カルシウム測定試薬の基礎的検討。
鞍津輪優子、岩切尚子、藪押利香、籠正利、栗山儀明
第44回宮崎県医学検査学会 2005年11月20日,宮崎市 - 迅速赤血球沈降速度測定装置クイックアイの基礎的検討。
黒木祥子、末澤滝子、吉野修司、籠正利
第44回宮崎県医学検査学会 2005年11月20日,宮崎市 - 手術時の手指消毒方法改善に向けての基礎的検討。
津曲洋明、横尾明子、大嶋雅代、谷口陽子、木佐貫篤
第44回宮崎県医学検査学会 2005年11月20日,宮崎市 - 肺腫瘍 pleomorphic carcinoma。
木佐貫篤
第288回九州沖縄スライドコンファレンス 2005年11月26日,大分市 - スライドカンファレンス:肺腫瘍 PleomorPhic carcinoma。
木佐貫篤
第5回えびのカンファレンス 2006年1月21日,えびの市 - 私の失敗した症例:肺腫瘤 Tuberculoma。
木佐貫篤
第5回えびのカンファレンス 2006年1月21日,えびの市 - Bucillamineによる薬剤性肺炎の一例。
今津善史、平塚雄聡、林英里香、深江裕子、石原旅人、藤浦芳丈、生島一平、石崎淳三、上田正人、木佐貫篤
第272回日本内科学会九州地方会 2006年1月28日,福岡市 - 成人鼠経ヘルニア根治術後クリティカルパスにおける鎮痛薬の定期内服の効果。
~術後在院日数と術後屯用鎮痛薬の使用回数について~
阿比留知子、木佐貫篤
平成17年度宮崎県看護研究学会 2006年3月18日,宮崎市
(その他)
- 便利はヒトをだめにする?。
木佐貫篤
日州医事 678:13-14,2006
【看護科】
(原著、著書、誌上発表)
- 手術時の手指消書方法改善に向けての基礎的検討。
津曲洋明、横尾明子、大嶋雅代、谷口陽子、木佐貫篤
宮臨技会誌86:31-35,2006
(学会、研究会発表)
- 事例発表:S状結腹痛のターミナル期で訪問看護を利用し24日間の在宅療養ができた事例。
県立日南病院緩和ケアチーム設立の経緯と活動内容の紹介。
野元敦子(県立日南病院緩和ケアチーム)
第120回在宅ケア研究会 2005年5月10日,日南市 - 鼠径ヘルニアパス(PHS法)。
阿比留知子
第4回宮崎医療連携研究会・第1回地域クリニカルパス大会 2005年5月20日,宮崎市 - 手術時手指消毒の有効な方法の基礎的検討~手洗い方法の改善に向けて~。
横尾明子、大嶋雅代、谷口陽子、木佐貫篤、津曲洋明、竹中美香
第7回医療マネジメント学会学術総会 2005年6月25日,福岡市 - 退院阻害因子の検討~地域医療連携部門と医療相談部門の連携の重要性。
黒木直子、神園健、木佐貫篤
第7回医療マネジメント学会学術総会 2005年6月25日,福岡市 - クリティカルパス展示:腹腔鏡下胆嚢摘出術。
荒川志保
第7回医療マネジメント学会学術総会 2005年6月24-25日,福岡市 - クリティカルパス展示:婦人科開腹術(子宮筋腫、卵巣、子宮外妊娠など)。
池田芳江
第7回医療マネジメント学会学術総会 2005年6月24-25日,福岡市 - 成人鼠径ヘルニア根治術パスにおいて鎮痛薬の定期内服が及ぼす効果。
阿比留知子、松田俊太郎、木佐貫篤
第4回医療マネジメント学会九州山口連合大会 2005年10月29日,福岡市 - 効率化と情報共有を目指したインシデント報告システムの改善。
阪元弘子、田中茂子、柿塚寿子、野口初代
第4回医療マネジメント学会九州山口連合大会 2005年10月30日,福岡市 - インシデントレポートを活かした業務改善活動。
河野穂波、田中茂子、柿塚寿子、野口初代
第4回医療マネジメント学会九州山口連合大会 2005年10月30日,福岡市 - クリティカルパス展示:成人鼠径ヘルニア根治術パス。
阿比留知子
第4回医療マネジメント学会九州山口連合大会 2005年10月29-30日,福岡市 - インシデントレポートを活かした業務改善活動の効果。
河野穂波、田中茂子、柿塚寿子、藤井みよ子、野口初代
平成17年度宮崎県看護研究学会 2006年3月18日,宮崎市 - 高次脳機能障害患者の経口摂取以降への働きかけ。
~経管栄養から経口摂取へと移行した事例を通して~
猪野美由紀、矢野美佳、黒木直子、野口初代
平成17年度宮崎県看護研究学会 2006年3月18日,宮崎市 - 光線治療を受ける児の母親に対する不安の軽減へのアプローチ。
~記録様式を改訂した効果~
鶴田由紀
平成17年度宮崎県看護研究学会 2006年3月18日,宮崎市 - インシデント報告システムの改善。
阪元弘子、田中茂子、柿塚寿子、野口初代
平成17年度宮崎県看護研究学会 2006年3月18日,宮崎市 - 成人鼠経ヘルニア根治術後クリティカルパスにおける鎮痛薬の定期内服の効果。
~術後在院日数と術後屯用鎮痛薬の使用回数について~
阿比留知子、木佐貫篤
平成17年度宮崎県看護研究学会 2006年3月18日,宮崎市 - 体位変換時に使用する三角枕改良の試み。
~大腿骨頸部骨折で牽引中の患者に使用して~(示説)。
太田有里子、高橋幸恵、黒田君代
平成17年度宮崎県看護研究学会 2006年3月18日,宮崎市
(講演)
- 退院計画調整における看護師の役割。
黒木直子
平成17年度県立病院等看護職員研修(基礎コース・ステップⅡ) 2005年5月24日,宮崎市・自治学院 - リスクマネジメントのABC~リスク感性を高めよう。
田中茂子
第9回県立日南地域連携セミナー 2005年10月4日,日南市 - 病院内の接遇について
山崎美鈴
串間市民病院職員研修 2005年10月5-6日,串間市 - 思春期教育~命の大切さを考える「性教育・命の大切さ」。
門川久子、中倉輝子
日南市細田中学校 2006年2月8日,日南市 - 思春期教育~命の大切さを考える「性教育・命の大切さ」。
門川久子、中倉輝子
日南市細田中学校 2006年2月15日,日南市 - 思春期教育~命の大切さを考える「性情報への対応」。
門川久子、中倉輝子
日南市立飲肥中学校 2006年2月17日,日南市 - 思春期教育~命の大切さを考える「生命の誕生」。
門川久子、中倉輝子
日南市立吾田中学校 2006年3月9日,日南市 - 思春期教育~命の大切さを考える「性非行、性犯罪」。
門川久子、中倉輝子
日南市立飲肥中学校 2006年3月10日,日南市 - 胃瘻のケア。
河野穂波
第10回県立日南医療連携セミナー 2006年3月10日,日南市
【地域医療連携室】
(学会、研究会発表)
- 退院阻害因子の検討~地域医療連携部門と医療相談部門の連携の重要性。
黒木直子、神園健、木佐貫篤
第7回医療マネジメント学会学術総会 2005年6月25日,福岡市
(講演)
- 退院計画調整における看護師の役割。
黒木直子
平成17年度県立病院等看護職員研修(基礎コース・ステップⅡ)
2005年5月24日,宮崎市・自治学院 - 病院における地域医療連携~それから見える問題。
木佐貫篤
特別養護老人ホーム幸楽荘職員研修会 2005年7月7日,西都市
(その他)
- 座談会:連携実務者が語る連携室の現実とこれから。
木佐貫篤、中山和則、三谷嘉章、瀬尾利加子、小泉一行
連携医療:3,76-79,2005
2. 院内発表・研修会等
(1) 臨床懇話会・合同カンファレンス
臨床懇話会は、医局全体のカンファレンスで各診療科持ち回りで発表を行う。テーマは自由であり、研修医レベルを基準とし研修医への教育も目的としている。昨年度は1月に特別講演会を開催した。7・8月を除く毎月第3水曜日定例医局会前の17時から30分間講堂にて実施している。
また、複数診療科や院外医師も交えた合同カンファレンスや研修会等も随時行っている。
| 日時 | 担当診療科 | 発表者 | 演題 |
|---|---|---|---|
| 4月20日 | 内科 | 生島 一平 | 不整脈 |
| 5月18日 | 小児科 | 麻田 智子 | 熱性痙攣 |
| 6月15日 | 耳鼻咽喉科 | 直野 秀和 | 注意を要する耳鼻科疾患 |
| 9月21日 | 麻酔科 | 田村 隆二 | 肺梗塞 |
| 10月19日 | 産婦人科 | 田中 博明 | 妊婦と薬剤 |
| 11月16日 | 眼科 | 福島 慶美 | 眼科の救急疾患 |
| 12月22日 | 泌尿器科 | 高森 大樹 | 前立腺生検 |
| 1月18日 | 病理 | 木佐貫 篤 | クリティカルパス |
| 2月15日 | (都合により中止) | ||
| 3月15日 | 外科 | 松田 俊太郎 | 内視鏡的胃瘻造設 |
(院内で開催されている主な合同カンファレンス・2005年度内容)
※院内で単独診療科開催のものは除く。
| 名称・参加診療科 | 開催日 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 外科・放射線科・病理 | 毎週月曜日 17時~18時 | 術前・術後症例検討 |
| 整形外科・放射線科・リハビリテ ーション科 | 毎週火曜日 8時~8時30分 | 術前・術後症例検討 |
| 南那珂消化器カンファレンス(外科、放射線科、病理、開業医) | 毎月第3木曜日 19時~20時 | 症例検討(2例〉、症例呈示、他 |
| 臨床抄読会 (産婦人科、産婦人科開業医) | 毎週金曜日 8時~8時30分 | 文献抄読、他 |
| 症例検討会・手術ビデオ討論会 (眼科、眼科開業医) | 毎月第3木曜日 19時~20時 | 症例検討、手術手技検討、他 |
(2) 院内講演会・教育研修会
病院職員の資質向上、円滑な業務運営及び医療事故防止等を目的として各種委員会・研究グループ等で随時講演会・研修会を企画して頻回に行われている。平成17年度に院内で開催されたものは下記の通り(各診療科企画の医師対象のみの講演会等は別記)。
| 開催日 | 講演会・研修会等の名称・内容 | 参加数 | 場所 | 主催 |
|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 病院機能評価の日記念講演会 「2004年認定病院の集い 報告」木佐貫 篤(臨床検査科) 「評価基準version5について」山口 もと代氏(前宮崎県看護協会会長) | 84名 | 講堂 | 病院機能評価委員会 |
| 5月11日 | 第11回クリニカルパス研究会 「パスとは?当院におけるパスヘの取り組みについて」木佐貫 篤(臨床検査科) 「ソケイヘルニアのパス」松田 俊太郎(外科)阿比留 知子(4西) | 43名 | 講堂 | クリニカルパス研究会 |
| 5月31日 | 勉強会「腹部エコーのABC」平松 百合子技師、三原 謙郎先生(県立宮崎病院) | 名 | 講堂 | 3東病棟 |
| 6月15日 | 心電図研修会 講師:岡田 保紀氏(メディカルシステム研修所所長) | 17名 | 講堂 | 看護科 |
| 6月17日 | 輸血研修会(看護師対象) 「血液製剤の取り扱いと輸血過誤防止について」押川 秀次氏(宮崎県赤十字血液センター医薬情報係) 「当院における血液製剤取扱い上の注意点」末渾 滝子(臨床検査科) | 36名 | 講堂 | 輸血療法委員会 |
| 6月29日 | インシデント報告会[事例報告] 藤井 みよ子(看護科)山口 正人(薬剤科) 田中 衛(放射線科)津曲 洋明(臨床検査科)池田 睦子(栄養管理科) | 60名 | 講堂 | 医療事故防止対策委員会リスクマネジメント部会 |
| 7月1日 | 院内感染研修会 「当院での手洗いについて」岡元 サエ子(3東) 「当院のICT(感染対策チーム)について」木佐貫 篤(臨床検査科) 「当院ICUの感染対策について」長田 直人(麻酔科) 「疥癬対策について」長嶺 英宏(皮膚科) 「結核の感染対策について」今津 善史(内科) 「当院の結核感染対策について」柿塚 寿子(看護科) 「新型インフルエンザについて」平塚 雄聡(内科) 「中央材料室の感染対策について」田中 茂子(中央材料室) | 62名 | 講堂 | 院内感染症対策委員会 |
| 7月5日 | 医療マネジメント学会参加報告会 「発表(手術時手指消毒の有効な方法の基礎的検討~手 洗い方法の改善に向けて~)」横尾 明子(手術室) 「発表(退院阻害因子の検討~地域医療連携部門と医療相談部門の連携の重要性)」黒木 直子(連携相談室) 「報告(パス関連演題)」竹中 美香(耳鼻咽喉科) 「報告(医療安全管理演題)」田中 茂子(中央材料室) 「報告(NST関連演題)」岩崎利恵(3東) 「報告(地域連携、院内感染関連演題)」木佐貫 篤(臨床検査科) | 36名 | 講堂 | 地域医療連携/医療相談室 |
| 7月6日 | 輸血研修会(医師対象) 「血液製剤の取扱いと輸血過誤防止について」押川 秀次氏(宮崎県赤十字血液センター医薬情報係) | 20名 | 講堂 | 輸血療法委員会 |
| 7月8日 | 医学講演会 「進行胃癌・大腸癌に対する化学療法の現状と展望」中野 修治先生(九州大学病態修復内科学助教授 | 20名 | 講堂 | 内科 |
| 7月12日・13日 | 電子カルテシステム・看護支援システムデモンストレーション(富士通担当者) | 講堂 | 事務局 | |
| 7月20日 | 放射線業務従事者教育訓練 「個人被爆線量について」「ガラスバッチの仕組み、装着方法」狩野 好延氏 (千代田テクノル) | 22名 | 講堂 | 放射線安全委員会 |
| 8月12日 | 緩和ケアチーム勉強会 「モルヒネのレスキュードーズについて」衛藤 浩一氏(大日本製薬(株)医薬情報担当) | 17名 | 第二会議室 | 緩和ケアチーム |
| 8月24日・26日 | 職員研修会 「宮崎県総合長期計画・元気みやざき創造計画について」 「宮崎県行政改革大網について」 「服務規律(接遇を含む)について」 | 132名 | 講堂 | 事務局 |
| 9月6日 | 接遇セミナー「豊かな感性と接遇」野崎 龍氏(学研) (台風のため中止) | 講堂 | 看護科接遇委員会 | |
| 9月8日 | 衛星遠隔研修実践特別講座 「個人情報保護法~医療現場おける留意点~」本田 茂樹氏(株インターリスク総研社会法務リスク部主席コンサルタント) | 30名 | 講堂 | 事務局 |
| 9月9日 | AED勉強会 | 40名 | 講堂 | 看護科救急委員会 |
| 9月14日 | 全面ディスポ化に向けての調査結果報告会 「手術用ガウン・シーツの全面ディスポ化について」 「全面ディスポ使用時のコストについて」 「ディスポ化のメリットについて」 | 20名 | 第二会議室 | 手術室 |
| 11月1日 | 第1回パス大会 「大腿骨頸部骨折パスver.9」有馬 沙智(5東) 「気管支鏡パス」今津 善史(内科)河野 英梨(6東) | 53名 | 講堂 | パス委員会 |
| 11月8日 | 第1回職業倫理講演会「患者苦情からみた医療倫理」柴田 紘一郎(院長) | 84名 | 講堂 | 教育研修委員会 |
| 11月25日 | 学習会「褥瘡の診断と治療」長嶺 英宏(皮膚科) | 30名 | 講堂 | 褥瘡対策委員会 |
| 12月10日 ~11日 | 固定チームナーシング研修会 西元 勝子氏(院外講師) | 158名 | 講堂 | 看護科教育部、看護師自治会 |
| 12月12日 | 交通安全法令講習会 川井 一男氏(日南警察署交通課交通係長) | 64名 | 講堂 | 事務局 |
| 12月15日 | 呼吸勉強会 長田 直人(麻酔科) | 21名 | 講堂 | ICU |
| 1月17日 | 臓器移植講演会 「県内腎臓移植の現状と今後の取り組みについて」重満 恵美氏(財団法人宮崎県腎臓バンク 移植コーヂィネーター) 「臓器移植のシステムと提供の手続きについて」塚本 美保氏(社団法人日本臓器移植ネットワーク西日本支部移植コーディネーター) | 45名 | 講堂 | 地域療連携室他 |
| 1月24日 | 第2回職業倫理講演会「点から立体」小川茂仁氏(日南学園高等学校野球部監督) | 60名 | 講堂 | 教育研修委員会 |
| 2月7日 | 第2回パス大会 1)前回発表パス経過報告 「大腿骨頸部骨折パスver.9」 内村 けい子(5東) 「気管支鏡パス」池元 淳子(6東) 2)「新しいパス作成基準と電子カルテにおけるパス」木佐貫 篤(病理) 「新しい作成基準に準じたパスの実例~ソケイヘルニアパス~」阿比留 知子(4西) | 56名 | 講堂 | パス委員会 |
| 2月22日 | TQM活動成果発表会 「地域がん診療拠点病院の活動」福田 雪子(看護科) 「楽しくバイキング」池田 睦子(栄養管理科) 「看護科リスクマネジメント委員会の取り組みについ て」柿奨 寿子(看護科) 「中央材料室の取り組み」 田中 茂子(中央材料室) 「バランスト・スコアカード 導入による地域連携業務のプラッシュアップ」木佐貫 蕉(地域医療連携/医療相談室) 「師長のキャリアをもっと活かそう」山崎 美鈴(看護科) | 41名 | 講堂 | 事務局 |
| 3月8日 | 電子カルテ運用説明会 | 講堂 | 事務局 | |
| 3月16日 | 平成18年度診療報酬改定研修会(衛星遠隔研修実践講座) 「診療報酬報酬改定~平成18年度診療報酬改定の概要 ~中林 梓氏(ASK梓診療報酬研究所所長 | 61名 | 講堂 | 事務局 |
(3) 看護科院内発表会
毎年、看護師自治会主催による院内看護研究発表会を行っている。又年に4回、土曜日半日を使い、持ち寄った事例の検討会を実施し、看護の質向上を目指している。
さらに卒後2年目・3年目の看護師には、卒後研修の一環として研究発表の場を設けている。
【第34回院内看護研究発表会】(2006年1月28日 講堂)
演題12題、講評:蔵重 幸子先生(参加 名)
- 手術待機中の家族への不安援助~手術進行画面表示を使用して~
手術室 古城由美、湯地尚子、松浦寿美 - 中央材料室で発生するインシデントの傾向~報告用紙の作成と分析~[紙上発表]
中央材料室 田中茂子 - ポジショニングの導入へのアプローチースタッフの意識の統一~
NICU 黒木美和、長田麻岐、多田栄子 - ブラウン氏架台カバー作製の試み
5東 大嘉田訓生、高橋幸恵、菊山順子、日高梨香、温水育美、黒田君代 - 胎児監視装置装着時の苦痛の緩和~安楽クッションを作製して~
4東 岸本智保、大久保誉子、蒲生由佳、畑田久美 - がん終末期にある患者の退院に向けた家族支援の検討
4西 池田史枝、日高由美子、橋本隆子 - 看取りに対する看護師のストレスとその解消法の一考察
~アンケート調査と茶話会形式のデスカンファレンスを行って~
6西 野口香奈子、自ヶ澤由美、川俣律子、広池麻衣子 - 退院調整シートの現状分析と運用方法の改善
6東 宮崎由紀子、浦壁陽子、川崎愛子、斉藤歌 - 入院時パンフレットの改善~患者サービス向上を目指して~
3東 足利美智子、佐藤さなえ、上園順子、西之園絵里、未留孝子 - 家族援助チェックリストの再検討~集中治療室における面会時の家族援助の充実を図る~
ICU 谷真淑、斉藤美和、那須智子 - 外来における待ち時間対策~ポケットベル使用を試みて~
外来 長友育代、押富順子、川畑裕子、鳥越恵子 - ウォーキングカンフアレンスの導入~情報の共有化を目指して~
5西 東弥生、白石直子、橋本萌、松山薫
【卒後2年目生ケースレポート発表】(2005年11月21日・11月29日 講堂)
- ストーマ造設患者への看護上のポイント
~ストーマケアについて不安のある患者との関わりを通じて~
3東 西之園 絵里 - 再入院・再手術に対して不安を持つ患者への関わり
3東 足利 美智子 - 生活環境が一変した妊婦が目標を設定できるまでの援助について
4東 藤元 美紀 - 緊急帝王切開術にて分娩された母親の看護
~分娩を振り返る時期と環境を検討する~
4東 後藤 朝美 - ターミナル期にある患者との関わりを振り返って
~死を目の前にした患者の思いから学んだこと~
4西 満森 未来 - 前向きな入院生活に向けての援助
左半身麻痺を持つ左大腿顆上骨折箇患者との関わりを通して
5東 大嘉田 訓生 - 転院により生活の場が変化した患者との関わりを通して学んだこと
5東 温水 育美 - 快の刺激を取り入れた関わり~口腔ケアを通して~
5西 橋本 萌 - 患者のセルフケア行動を支える看護~透析導入する患者の関わりを通して~
6東 斉藤 歌 - 退院後自己管理が必要となった患者への看護
6東 川崎 愛子 - 老年期に糖尿病と診断された患者との関わりを振り返って
6西 金丸 あさみ - セルフケア能力向上のための援助
~気管切開、胃ろう造設している患者との関わりを通して~
6西 後藤 由美子 - 痛みのある患者の看護について
3東 陶山 理奈 - コミュニケーション困難な患者との関わり
ICU 那須 智子 - 緊急帝王切開術となった産婦への看護を考える
4東 蒲生 由佳 - 母児同室中の母親との関わりを振り返って
NICU 黒木 美和 - ターミナル期看護について考える-余命告知を受けた患者から学んだこと-
4西 橋口 奈緒美 - 退院を目前にした患者への看護
~不眠を訴えナースコールの多い患者との関わりを通して~
4西 松浦 香奈 - 変形性股関節症患者への援助~退院指導と退院後のフォローを通して~
5東 菊山 順子 - 家族の意向に沿った退院調整~障害を持った患者の退院までの関わりを通して~
5西 白石 直子 - 喉頭摘出術後の訴えが少ない患者への効果的な看護介入~交換ノートを活用して~
5西 松山 薫 - リハビリテーションを積極的にすすめるための看護~自己の関わりを振り返って~
6東 宮崎 友紀子 - 終末期にある患者を支える家族とのかかわりを振り返って
6西 広池 麻衣子 - 血液透析導入患者の看護~受け持ち看護師としてのかかわりを通して学んだこと~
6西 野口 香菜子
【卒後3年目生看護研究発表】(2005年12月5日・12日 講堂)
- 同室者との人間関係によるストレスへの看護
~事例を通して考える、看護者に求められる関わり~
4東 濱山 望
指導者 畑田 久美 - 重症心身障害児の退院指導の検討
4西 黒木 麻未
指導者 徳田 美喜 - 自宅退院に向けての患者、家族への関わり
5西 井手 真季
指導者 矢野 美佳 - ICUにおける面会規則の現状
~アンケート調査、予後不良となり面会緩和を行った事例を振り返って~
ICU 川上 美知子
指導者 竹井 絵美 - 高次脳機能障害の患者の経口摂取移行への働きかけ
~経管栄養から経口摂取へと移行した事例を通して~
5西 猪野 美由紀
指導者 矢野 実佳 - 選択記述式のパースプランを使用して検討
4東 原田 望美
指導者 畑田 久美 - 大腿骨頸部骨折・変形性股関節症の術後患者に対する自助具の有効性
~商品化された靴べらを改良して~
5東 石三 奈津子
指導者 高橋 幸恵 - 与薬方法に対する看護師の判断過程の検討~与薬基準を作成して~
6西 林 奈緒子
指導者 井上 千鶴子 - 「睡眠」への援助 ~プロセスレコードを通して~
4西 藤丸 誠司
指導者 徳田 美音 - 傾聴するという看護 ~訴えの多い患者に関する看護を振り返って~
6東 迫田 久弥子
指導者 松本 万里子 - 全身麻酔手術によるこりの出現割合とその緩和に向けての援助
3東 竃 友実
指導者 高原 富美恵 - 体位変換時に使用する三角枕改良の試み ~大腿骨頸部骨折で牽引中の患者に使用して~
5東 太田 有里子
指導者 高橋 幸恵 - 効果的な患者指導を行うために ~チェックシートの一検討~
6西 新福 葉子
指導者 井上 千鶴子 - 患者さんから学んだ家族援助の必要性
6東 河野 英梨
指導者 松本 万里子 - 女性生殖器疾患開腹手術後の退院指導の検討~患者アンケートをもとに~
4東 岸本 智保
指導者 畑田 久美 - 成人鼠経ヘルニア根治術クリティカルパスにおける鎮痛薬の定期内服の効果
~術後在院日数と術後屯用鎮痛薬の使用回数について~
4西 阿比留 知子
指導者 徳田 美音 - ターミナル期における患者・家族への援助
5西 武田 真紀子
指導者 矢野 美佳 - 患者家族への関わり方の変化 ~2つのプロセスレコードを通して~
ICU 寺名 亜里沙
指導者 竹井 絵美 - 光線療法を受ける児の母親に対する、不安の軽減のアプローチ ~記録様式を改訂した効果~
NICU 鶴田 由紀
指導者 畑田 久美 - 父親の面会時間に関する意識調査 ~NICUにおける面会時間の延長を通して~
NICU 富山 あゆみ
指導者 畑田 久美 - オムツによる悪臭の改善 ~お茶柄による消臭を試みて~
6西 上村 海津子
指導者 井上 千鶴子
| 日時 | 発表病棟 | 座長 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 5月20日 | 透析室 | 黒木直子 | 79才の男性で維持透析の患者:看護師の指導に対して納得されず指導を受け入れられない。今後スタッフはどのように関わっていったらいいのか。 |
| 2005年 | 手術室 | 池田芳江 日高由美子 |
手術室では患者は大なり小なり、何らかの不安を持って入室してくる。術前訪問では問題のなかった患者が、入室と同時に言動が不安定になり落ち着かない表情も見られたが、すぐその変化に気付くことができ、不安の軽減につながった。手術前のよい関わりについて考えたい。 |
| 透析室 | 医師や看護職が再三介入し、指導を強化しても体重増加が著しい患者に対して、指導の難しさを感じている。このような自己管理がうまくできない患者に対する関わり方についてどうすればよいか助言をうけたい。 | ||
| 9月10日 | 6東 | 河野穂波 井山久美子 |
腰痛圧迫骨折で入院中の患者が、ペインコントロールをうけいれず入院が長引いている。内服や低周波の治療は受けている。今後の方向性が決まらない。どのように関わればよかったか。 |
| 5東 | 変形性股関節症の手術目的で入院した思春期の女性、術前の指導や治療に対して協力が得られず関わりが難しかった。不安定な時期にある患者や協力が得られない患者との関わりについて検討してほしい | ||
| 11月5日 | 5西 | 内村けい子 井手京子 |
高齢で夫婦2人暮らし、子供は遠方である。夫が入院したが退院後の生活について妻に決定能力が無い。本人や家族の希望に添った退院援助について、ともに考える機会としたい。 |
| NICU | 重度の先天性疾患児を出生した未検診の褥婦との関わり、積極的な加療はしないことになったが、家族の思いを尊重して看取りの看護を行った。母親もスタッフも満足する結果となったが、もっとできることがあったのではないかと思って事例とした。 | ||
| 2006年 2月14日 |
ICU | 福田雪子 | 医療者に不信感をあらわにする言動がみられた患者の妻や家族に対して、家族の気持ちを考慮した看護や関わりに心がけ、関係を好転できたのではないかと考えた。 |
| 6西 | 迫間やす子 | 発語や体動がなくなり、食欲減退・飲水困難がある患者に対して、症状改善のための水分摂取を目標とした関わりが困難であった。もっと効果的な関わりもあったかもしれないと考えた。 |
3. 病理解剖
平成16年度まで日本病理学会認定病院Bに認定されていたが、剖検数が少ない状態が続いたことより平成17年度より登録施設として認定されることとなった。平成17年度も前年同様10件以下と少ない状態が続いている。当院は管理型研修指定病院として認められたことから、研修医の教育のためにも件数増が望まれる。
| 診療科 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 科 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 死亡数 | 19 | 19 | 23 | 22 | 21 | 17 | 22 | 15 | 29 | 26 | 25 | 18 | 256 |
※死亡数には、外来及び救急外来死亡も含む
| /年度 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総剖検数 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 院内剖検数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| (死産児) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 院外受託剖検数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 院内死亡数 | 221 (205) |
208 (183) |
271 (244) |
256 (224) |
256 (228) |
| 総剖検率(%) | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 0.8 |
| 院内剖検率(%) | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.9 |
※総剖検数は、死産児・受託解剖等当院で行われたすべての剖検数
※院内剖検数は、入院患者の剖検数(死産・外来・受託解剖を除く)
※院内死亡数の( )は、外来及び救急外来死亡を除いた数
※総剖検率(%)=(受託解剖を除くすべての剖検数)/(総死亡数、外来・救急外来死亡を含む)×100
※院内剖検率(%)=(入院患者剖検数、死産・外来・救急外来死亡を除く)/(入院患者死亡数、死産・外来・救急外来死亡を除く)×100
| 日時 | 診療科 | 症例(病理診断) |
|---|---|---|
| 2005年5月19日 | 整形外斜 | 心筋梗塞(急性貫壁性及び陳旧性) |
| 2005年6月28日 | 内科 | 大動脈弁狭窄症、左心室肥大 |
4. 県立日南病院で開催された学会
| 学会名称・内容 | 学会長 | 開催年月 | 場所 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|
| 289回九州沖縄スライドコンファレンス | 木佐貫 篤(世話人) | 2006.1.14 | 講堂 | 67名 |
5. 各診療科等が主催した講演会・研究会等
| 担当科 | 講演会・研究会等の名称・内容 | 参加者 | 開催年月 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 眼科 | 県南勉強会(延べ12回) | 毎月 第三水曜日 | 地域医療室 | |
| 病理他 | 第42回南那珂消化器カンファレンス (症例検討:胃癌2例) | 18名 | 2005.4.21 | 講堂 |
| 看護科 | 衛星遠隔研修(看護ケア)講座 「看護記録」個人情報保護法とフォーカスチャーテイ ング | 58名 | 2005.4.28 | 講堂 |
| 病理他 | 第43回南那珂消化器カンファレンス (症例検討:胃癌2例) | 14名 | 2005.5.19 | 講堂 |
| 地域医療連携室 | 第8回県立日南地域連携セミナー「間違いだらけの心電図の勉強法~不整脈編~」藤浦芳丈(内科) | 135名 | 2005.5.24 | 講堂 |
| 看護科 | 衛星遠隔研修(看護ケア)講座 「スキルアップI」知っておきたい薬の知識・薬のリスクマネジメント | 55名 | 2005.5.26 | 講堂 |
| 病理他 | 第44回南那珂消化器カンファレンス (症例検討:胃GIST、膵頭部癌) | 14名 | 2005.6.16 | 講堂 |
| 外科他 | 急性肺障害の病態と治療研究会(南那珂医師会生涯教育医学会) 「人工呼吸管理にて救命し得たクラミジア肺炎を合併したじん肺症の一例-シベレスタットナトリウムの使用経験-」今津 善史(内科)他 「集中治療により救命し得た胆汁性腹膜炎の1例」松田 俊太郎(外科)他 特別講演「敗血症における鉄器障害メカニズムと治療戦略」垣花 泰之先生(鹿児島大学集中治療部講師) | 2005.6.23 | 第二会議室 | |
| 看護科 | 衛星遠隔研修(看護ケア)講座 「感染管理」実例で学ぶ感染管理-ベッドサイドケアにおける感染対策- | 61名 | 2005.6.23 | 講堂 |
| 病理他 | 第45回南那珂消化器カンファレンス (症例検討:胃癌2例) | 15名 | 2005.7.21 | 講堂 |
| 看護科 | 衛星遠隔研修(看護ケア)講座 「スキルアップ」研究の活かし方一研究テーマの絞り込みの実際- | 19名 | 2005.8.25 | 講堂 |
| 病理他 | 第46回南那珂消化器カンファレンス (症例検討:胃癌2例) | 12名 | 2005.9.15 | 講堂 |
| 内科他 | 糖尿病をまなぶ会講演会「各施設の糖尿病に対する取り組み報告」「インスリン治療の最新情報」 特別講演「私見-メタポリックシンドロームの考え方」及川 眞一先生(日本医科大学第3内科内分泌代謝内科教授) | 名 | 2005.9.16 | 講堂 |
| 臨床検査科 | 県南地区検査技師勉強会「輸血前後の感染症検査こついて」五関 茂氏(オーソクリニカルダイアグノスティック) | 10名 | 2005.9.20 | 第一会議室 |
| 看護科 (緩和ケア チーム) | 緩和ケア研修会「マーガレットニューマンの看護理論 について」遠藤 恵美子先生(宮崎県立看護大学教授) | 53名 | 2005.9.21 | 講堂 |
| 看護科 | 衛星遠隔研修(看護ケア)講座 「臨床緩和ケア」~東札幌病院の実践~ | 37名 | 2005.9.22 | 講堂 |
| 地域医療連携室 | 第9回県立日南地域連携セミナー 「リスクマネジメントのABC~リスク感性を高めよう」田中 茂子(中央材料室) | 99名 | 2005.10.4 | 講堂 |
| 看護科 ・看護協会 | 看護ネットワーク研修「看護の資向上を考える」 | 77名 | 2005.10.20 | 講堂 |
| 看護科 | 衛星遠隔研修(看護ケア)講座 「リスクマネジメント」ヒヤリハットの実例と解説- 患者、家族指摘事例を中心に- | 77名 | 2005.10.27 | 講堂 |
| 看護科 (3東) | 第6回オストメイト交流会「超消臭カバーについて」久保野氏(丸愛産業株式会社)「装具について」藤丸氏 (コロプラスト株式会社)座談会 | 35名 | 2005.10.29 | 講堂 |
| 臨床検査科 | 第1回いせえびカンファレンス(日南細胞診研修会) 細胞診鏡検実習(50症例) | 15名 | 2005.11.5 | 第二会議室 |
| 病理他 | 第47回南那珂消化器カンファレンス 「ESDについて」山本 雄一郎(放射線科)、症例検討:胃ESD症例2例 | 11名 | 2005.11.10 | 講堂 |
| 放射線科 | 日南・串間地区放射線技師研修会 「コドニクス ドライイメージャの説明」 | 20名 | 2005.11.11 | 講堂 |
| 病理他 | 第48回南那珂消化器カンファレンス (症例検討:胃癌1例、胃ESD症例1例) | 12名 | 2005.12.1 | 講堂 |
| 看護科 | 衛星遠隔研修(看護ケア)講座 「糖尿病看護」~どこにでもいる糖尿病患者さんの一歩進んだ糖尿病ケア~ | 20名 | 2005.12.22 | 講堂 |
| 病理他 | 第49回南那珂消化器カンファレンス (症例検討:胃癌2例) | 10名 | 2006.1.19 | 講堂 |
| 看護科 | 衛星遠隔研修(看護ケア)講座 「心理と病理」リハビリメイクとは | 68名 | 2006.1.26 | 講堂 |
| 産婦人科 | 宮崎県周産期症例検討会 | 2006.1.27 | 第二会議室 | |
| 病理他 | 第50回南那珂消化器カンファレンス (症例検討:胃癌、胃癌+胃潰瘍) | 15名 | 2006.2.16 | 講堂 |
| 地域医療連携室 | 第10回県立日南医療連携セミナー 「胃瘻の構造について」松田 俊太郎(外科) 「胃瘻のケア」河野 穂波(6西) | 140名 | 2006.3.10 | 講堂 |
| 看護科 | 衛星遠隔研修(看護ケア)講座 「がん看護」 | 21名 | 2006.3.23 | 講堂 |
6. 当院医師が担当した座長等の記録
| 診療科 | 医師氏名 | 学会等名称 | セッション名 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 柴田紘一郎 | 第22回日本呼吸器外科学会総会 | Invited Lecture:Exploration of the last anatomic frontier of thoracic surgery-the trachea | 2005.6.2 | 京都市 |
| 外科 | 市成 秀樹 | 第6回第二外科懇話会 | 呼吸器外科セッション | 2005.9.3 | 宮崎市 |
| 外科 | 市成 秀樹 | 平成17年度成人病検診従事者研修会 | 講演「肺結節診断-画像診断とCTガイド下肺生検」 | 2006.2.11 | 宮崎市 |
| 臨床検査科 | 木佐貫 篤 | 第285回九州沖縄スライ ドコンファレンス | 一般演穎(第7-8席) | 2005.5.14 | 福岡市 |
| 臨床検査科 | 木佐貫 篤 | 南那珂地域保健医学会 | 特別講演「キレイはビョーキだ -アレルギー疾患とその意外な背景-」 | 2005.6.30 | 日南市 |
| 臨床検査科 | 木佐貫 篤 | 第21回日本臨床細胞学会九州連合会学会 | 一般演題 | 2005.9.3 | 佐賀市 |
| 臨床検査科 | 木佐貫 篤 | 南那珂医師会医学会 | 特別講演「臨床医と倫理-Clinical Ethicsとは-」 | 2005.11.14 | 日南市 |
| 看護科 | 野元 敦子 | 第44回宮崎県看護研究学会 | 一般演題 | 2006.3.18 | 宮崎市 |
平成17年度 第2章 地域連携・交流・貢献
1. 地域医療連携/医療相談室の活動
(1) 平成17年度の地域医療連携室の取り組み
病院完結型医療から地域完結型医療への転換が求められる現在、中核病院には地域医療機関をはじめとする地域との接点となるべき部門の設置が求められている。
当院でも平成15(2003)年4月7日に地域医療連携室が設置(医療相談室との併設)され、平成16(2004)年4月からは常勤スタッフ3名を含む4名体制となり、各種活動を行っている。
17年度も前年度に引き続き紹介率30%達成・退転院調整充実・地域連携の推進、を大きな目的と掲げて様々な取り組みを行った。それにより17年9月以降紹介率が目標の30%を超えるなどの成果を得ることが出来た。また積極的に活動の成果を学会等でも発表した。
(2) 連携室の目標
当院理念「地域社会に貢献する病院」の実現
- 患者家族・地域医療機関・当院スタッフの間の相互理解を深め、患者を巡る様々な問題を解決し患者中心の医療が円滑に遂行できること
- 日南病院を中心に地域全体の医療レベルが向上するための活動をサポートすること
それらを通じ南那珂地域の住民に満足度の高い
良い医療を提供することを目指している
(3) 連携室の組織とスタッフ
連携室は、院内措置にて医事係内の独立部門として位置付けられており、1階の医療相談室、地域連携室に設置されている。
| 氏名 | 役職 | 勤務体制 | 役割分担 | |
|---|---|---|---|---|
| 室長 | 木佐貫 篤 | 検査科・医長 (南那珂医師会理事) | 兼任 | 総括 |
| 係 | 中野 浩 | 医事係・主査 | 専任 | 医療相談 |
| 係 | 迫間 やす子 | 看護科・主任看護師 | 専任 | 地域連携、看護相談 |
| 係 | 井上 百恵 | 嘱託職員(ニチイ) | 専任 | 事務(紹介状管理、統計作成、各種書類作成等) |
(4) 平成17年度の主な活動報告と成果
連携室では、(1)医療相談業務(2)地域連携業務(3)院内テレビ放送業務を行っているが、以下地域連携業務の主な取り組み・活動と成果について述べる。
平成17年度に取り組んだ主な地域連携業務は下記の通りである。
- 連携実績の把握(実績収集とデータベース化、各種統計作成) ※医事係と協力実施
- 退院後の療養先に関する相談(療養型病院・介護施設等の紹介、転院調整、在宅サービス確認等)
- 地域連携に関する情報提供
- 地域連携に関する情報収集
- 各種研修の実施、運営等(医療連携セミナーなど)
1)連携実績の把握(実績収集とデータベース化、各種統計の作成)
医事係と協力して各医療機関別の紹介数・逆紹介数を毎月把握し実績を確認している。
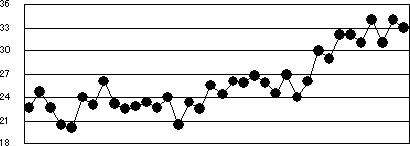
平成16年度後半から紹介率が25%を超える状況であったが、連携の推進及び平成17年7月よりの特定療養費導入(非紹介患者対象)などにより、9月より30%を超える状況となった。それに伴い平成18年1月より紹介外来加算取得を開始することができた。初再診合計の紹介患者数も4,926名(前年4,289名)と前年比637名増加(連携室調べ)した。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紹介件数 | 383 | 348 | 413 | 427 | 402 | 443 | 409 | 420 | 386 | 416 | 440 | 439 |
| 紹介率 | 26.7 | 24.4 | 25.8 | 29.8 | 28.9 | 31.5 | 32.3 | 30.9 | 34.3 | 31.1 | 34.2 | 33.4 |
(紹介件数は初再診全て含む)
2)退院後の療養先に関する相談
平成16年度から退院調整担当看護師が専任となったことが大きく、前年度以上に患者転退院に関する相談や調整がスムーズにすすみ、患者家族の満足度向上及び院外施設との連携に大きな成果を得ることが出来た。処理件数も139件と前年比156%増であった。 (平成17年度コンサルテーションシート運用実績)平成18年9月現在 提出件数:139件(解決済139件)
内訳 転院82件(病院65件、施設等17件)、在宅42件、他15件
- 対象患者在院日数:平均93.1日(1~1,480日)
- 解決までに要した日数:平均46.3日(1~291日)
調整には後方連携対象の病院が少なく解決まで時間がかかるなどの困難さから約1ヶ月程度要する。早期退院支援にむけてスクリーニングシート導入などの検討を行っている。
3)地域連携に関する情報提供
- 「日南病院診療案内-紹介受診の手引き-」発行(院外向け)
当院の診療状況・機能を案内する目的で、平成15年1月から作成配布しており、医師会の先生等より好評を得ている。発送先は南那珂2市2町全ての病院・診療所、医療関連施設など約200カ所におよぶ。当院は、医師の異動が多いため半年毎に改訂発行した。
(第6版:平成17年9月,第7版:平成18年2月) - 「連携室だより」「連携インフォメーション」の発行(院内向け)
病院訪問結果や院外の様々な情報を院内職員へ伝達する目的で、「連携室だより(スマイル通信)」「連携インフォメーション(院内メール)」として随時様々な情報を提供した。
4)地域連携に関する情報収集
- 地域医療機関訪問・情報交換
地域の医療機関の現状確認・連携室PRを目的に、17年度も2回施設訪問をおこなった。 - 各種会議等への出席 南那珂在宅ケア研究会(毎月第2火曜日)、南那珂緩和ケア研究会、南那珂地域ケア会議(年3回)、等の会議に出席し、情報交換などを通じて連携を深めている。
5)各種研修の実施、運営等
- 県立日南医療連携セミナー 圏域内医療機関等との交流、レベルアップ・連携推進を目的として、昨年に引き続き3回実施し好評を得た。
| 開催日時 | 内容 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 2005.5.24 第8回 | 「間違いだらけの心電図の勉強法(2)~不整脈編」 藤浦 芳丈(内科) | 135名 |
| 2005.10.4 第9回 | 「リスクマネジメントのABC~リスク感性を高めよう」 田中 茂子(看護科中央材料室師長) | 99名 |
| 2006.3.10 第10回 | 「胃瘻の構造とは」松田 俊太郎(外科) 「胃瘻のケア」 河野 穂波(看護科6西主任看護師) | 140名 |
- スマイル会-南那珂地区透析施設看護師勉強会 透析に関する勉強会の運営を連携室でサポートしている。
(平成17年度は当院での開催は無し) - 衛星遠隔看護研修講座(看護ケア講座)(看護科主催)
平成16年6月から毎月1回当院で開催しており、広報等に連携室が協力した。 - 在宅酸素重症児連絡会(小児科主催、連携室協力)
当院管理の在宅重症児について、当院小児科医師を中心に情報交換を行いよりよい対応をめざす会。参加者は医療(病院、訪問ステーション)、福祉(行政、保健所)、消防等。
第3回 2005年7月5日 21名参加
第4回 2005年11月1日 19名参加
第5回 2006年2月28日 20名参加 - 院内研修の院外オープン化 緩和ケア講演会、オストメイト交流会など院外から参加可能な研修も随時広報を行った。
2. 南那珂医師会との協力・連携
(1) 医師会運営への協力
地元2市2町の医師会である南那珂医師会には、木佐貫篤医長(臨床検査科)が理事に任命され、運営に参加して医師会と当院の連携に努めた。
(2) 医師会による夜間救急センター診療応援
南那珂医師会との話し合いにより、平成17年12月~平成18年3月の土曜日準夜帯(15回)に南那珂医師会会員(11名)による当院当直応援がおこなわれた。医師会の先生方からは、時間外救急体制に関して様々な意見が出された。
(3) 学校心臓検診への協力
医師会が自治体より委嘱され実施している学校心臓検診について、上田正人部長(内科)が判定委員として参加しており、精密検査を当院内科・小児科にて実施した(串間市の小中学生を除く)。
(4) 在宅ケア、緩和ケアへの関わり
南那珂医師会主催の「南那珂在宅ケア研究会」(毎月第2火曜19時?20時、南那珂医師会館)には、当院看護科・地域医療連携/医療相談室(連携相談室)もメンバーとして参加しており、毎回数名出席している。平成17年5月例会では、野元敦子看護師長(4西)が事例発表(在宅療養ができたターミナル期患者さん)と家族会の紹介を行った。
平成14年12月に発足した「南那珂緩和ケア研究会」には、当院から幹事として清水サナエ主任看護師(手術室、緩和ケアグループ)が参加している。
3. 地域諸機関からの研修・見学等
県立日南病院では、地域との医療連携充実及び明日の医療を担う人材育成のために、南那珂地区をはじめとする各教育機関、また消防署や地域医療機関等からの研修・見学等を毎年受け入れている。
平成15年度から宮崎大学医学部6年生のクラークシップを受け入れることになり、平成17年度は26名(内科・神経内科10名、外科4名、整形外科1名、耳鼻咽喉科2名、放射線科6名、臨床検査科3名)を受け入れた。
平成17年度の各種実習研修等の受け入れ実績は次のとおりである。
(1) 教育機関等
大学、短期大学、高等学校の実習見学受け入れ
| 期間 | 受け入れ科 | 主な実習内容 |
|---|---|---|
| 4月 4日 ~ 4月15日 | 内科・神経内科(2名) 放射線科(1名) 臨床検査科(1名) |
内科・神経内科全般 放射線科全般 病理全般 |
| 4月18日 ~ 4月29日 | 内科・神経内科(2名) 放射線科(1名) |
内科・神経内科全般 放射線科全般 |
| 5月 9日 ~ 5月20日 | 内科・神経内科(2名) 外科(1名 ) 臨床検査科(1名) |
内科・神経内科全般 外科全般 病理全般 |
| 5月23日 ~ 6月 3日 | 内科・神経内科(2名) 外科(1名 ) |
内科・神経内科全般 外科全般 |
| 6月 6日 ~ 6月17日 | 内科・神経内科(1名) 外科(1名 ) 放射線科(1名) 臨床検査科(1名) |
内科・神経内科全般 外科全般 放射線科全般 病理全般 |
| 6月20日 ~ 7月 1日 | 内科・神経内科(1名) 外科(1名 ) 放射線科(1名) 耳鼻咽喉科(1名) |
内科・神経内科全般 外科全般 放射線科全般 耳鼻咽喉科全般 |
| 7月 4日 ~ 7月15日 | 耳鼻咽喉科(1名) 放射線科(1名) |
耳鼻咽喉科全般 放射線科全般 |
| 7月18日 ~ 7月29日 | 整形外科(1名) 放射線科(1名) |
整形外科全般 放射線科全般 |
| 期間 | 学校名 | 主な実習内容 |
|---|---|---|
| 11月 7日 ~ 11月11日 | 活水女子大学(2名) | 栄養管理・給食管理 |
| 2月13日 ~ 3月 3日 | 南九州大学(2名) | 栄養管理・給食管理 |
| 期間 | 学校名 | 実習生数 | 主な実習内容 |
|---|---|---|---|
| 5月 9日~7月15日 | 宮崎リハビリテーション学院(3年) | 1名 | 長期臨床実習 |
| 6月27日~9月 2日 | 玉野総合医療専門学校(4年) | 1名 | 長期臨床実習 |
| 7月18日~9月23日 | 神村学園医療福祉専門学校(3年) | 1名 | 長期臨床実習 |
| 8月15日~10月 7日 | 常葉学園医療専門学校(4年) | 1名 | 長期臨床実習 |
| 8月22日~10月28日 | 宮崎リハビリテーション学院(3年) | 1名 | 長期臨床実習 |
| 10月31日~11月18日 | 神村学園医療福祉専門学校(2年) | 1名 | 評価実習 |
| 10月31日~12月 9日 | 第一リハビリテーション学院(3年) | 1名 | 長期臨床実習 |
| 1月16日~1月27日 | 宮崎リハビリテーション学院(2年) | 2名 | 評価実習 |
| 2月13日~2月24日 | 宮崎リハビリテーション学院(2年) | 2名 | 評価実習 |
| 3月 6日~3月17日 | 第一リハビリテーション学院(2年) | 2名 | 評価実習 |
| 期間 | 学校名 | 実習生数 | 主な実習内容 |
|---|---|---|---|
| 7月19日~8月12日 | 福山大学 | 1名 | 薬学部4年次生 |
| 1月30日~2月24日 | 福岡大学 | 1名 | 薬学部3年次生 |
| 期間 | 学校名 | 実習生数 | 主な実習内容 |
|---|---|---|---|
| 8月22日~9月 2日 | 麻生医療福祉専門学校福岡校 | 1名 | 入院・外来業務 会計・レセプト業務 |
実習受入期間:2005年5月~2006年3月
| 学校名 | 課程 (修業年限) |
学年 | 実習生数 | 実習期間 (延べ日数) |
実習病棟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県立看護大学 | 看護学士(4年) | 3年 | 30名 | 4241日 | 4東(NICUを含む)産科外来 |
| 4年 | 4名 | 56日 | 5東、6西 | ||
| 日南学園看護専攻科 | 看護師(2年) | 1年 | 40名 | 400日 | 3東、4西、5東、5西、6東、6西 |
| 2年 | 36名 | 2016日 | 3東、4東、4西、5東、5西、6東、6西 | ||
| 日南学園高校看護科 | 看護師(3年) | 1年 | 28名 | 56日 | 3東、4西、5東、5西、6東、6西 |
| 2年 | 23名 | 230日 | 3東、4西、5東、5西、6東、6西 | ||
| 3年 | 42名 | 545日 | 3東、4西、5東、5西、6東、6西 | ||
| 日南学園田野看護専攻科 | 看護師(2年) | 2年 | 31名 | 248日 | 4東 |
| 日南看護専門学校 | 看護師(3年) | 1年 | 38名 | 266日 | 3東、4西、5東、5西、6東、6西 |
| 2年 | 43名 | 1497日 | 3東(ICU含む)、4西、5東、5西、6東、6西、4東、小児科外来、OP室、透析室 | ||
| 3年 | 34名 | 1395日 | 3東(ICU含む)、4西、5東、5西、6東、6西、4東、透析室 | ||
| 合計 | 349名 | 7133日 | |||
【ふれあい看護体験】
これからの社会を担っていく高校生と病院、施設関係者が交流することで医療や看護について共に考えていくきっかけを作ること、また患者さんとふれあう体験を通して、看護する喜び・社会における看護の役割を理解し、看護の大切さや人の命について理解と関心を深める機会を提供することなどをねらいとして「ふれあい看護体験」を実施した。
| 日時 | 平成17年7月28日(木)9:00~15:15 | ||
|---|---|---|---|
| 参加対象 | 県立都城西高等学校 | 8名 | |
| 県立泉ヶ丘高等学校 | 5名 | ||
| 県立日南高等学校 | 9名 | ||
| 日南学園高等学校 | 3名 | ||
| 計 25名 | |||
| 実施病棟 | 全病棟7ヶ所 (3東・4東・4西・5東・5西・6東・6西) | ||
| 体験内容 | ~ 看護の心をみんなの心に~ 見る!触れる!学ぶ! |
||
| (1)清潔の援助(シャンプー、足浴など) | |||
| (2)体温・血圧・脈拍測定 | |||
| (3)食事の援助 | |||
| (4)体位と姿勢(車椅子搬送など) | |||
| (5)身の回りの世話・環境整備 | |||
| (6)排泄の援助 | |||
| (7)活動(散歩・運動・患者さんとの会話) | |||
(2) 行政機関等
【消防署】
| 研修期間 | 研修者、人数 | 主な研修内容 |
|---|---|---|
| 5月16日~6月10日 | 日南市消防本部消防士長 1名 | 救急患者の初期治療 |
| 2月15日 ~ 28日 | 日南市消防本部消防士長 1名 | 救急患者の初期治療 |
| 研修期間 | 研修者、人数 | 主な研修内容 |
|---|---|---|
| 3月 9日 ~ 11日 | 日南市消防署員 3名 | 救急室での見学、救急患者の応急処置 |
| 3月16日 ~ 18日 | 日南市消防署員 3名 | 救急室での見学、救急患者の応急処置 |
3)救急救命士気管挿管実習
平成17年度から救急救命士による気管挿管実習を開始した。これは手術室で全身麻酔を受けた患者に対して実際に気管挿管の実習を行うもので、実習に際しては麻酔科の専門医師が常時付き添って救急救命士の指導にあたり安全性を確保しながら行っている。
| 研修期間 | 研修者、人数 | 主な研修内容 |
|---|---|---|
| 2005年5月18日~2006年3月31日 | 日南市消防本部消防士長 1名 | 全身麻酔時における気管挿管実習 |
4)MC(Medical control)検証会
平成15年度からMC(Medical control)検証会を開始した。これは、救急救命士と当院医師等が出席して、実際に行われた救急出動の事例を検証することで今後の活動に役立て、あわせて救急救命士の技量向上を目的として行われている。
平成17年度の実施状況は、次のとおりである。
| 開催回数 | 日 時 | 内 容 | 出席者 |
|---|---|---|---|
| 第6回検証会 | 2005.5.30 | 検証 除細動 1事例 その他 7事例 | 医師1名 日南市消防署 12名 串間市消防署 2名 |
| 第7回検証会 | 2005.7.25 | 検証 除細動 1事例 その他 1事例 | 医師1名 日南市消防署 6名 串間市消防署 4名 |
| 第8回検証会 第9回検証会 | 二次検証会は実施せず | ||
| 第10回検証会 | 2006.1.30 | CAP 1事例 その他 1事例 | 医師1名 日南市消防署 8名 串間市消防署 4名 |
(3) 地域の医療機関等
| 研修期間 | 研修者、人数 | 主な研修内容 |
|---|---|---|
| 2006年 3月28日 | 日南薬剤師会会員 15名 | 電子カルテシステム導入について |
| 研修期間 | 研修者、人数 | 主な研修内容 |
|---|---|---|
| 2005年 7月15日 アトル日南店 |
日南薬剤師会・病院薬剤師会会員 40名 | ・デュロテップパッチと最近の麻薬製剤について ・医療を取り巻く個人情報の取り扱いについて |
| 研修期間 | 研修者、人数 | 主な研修内容 | 受け入れ病棟 |
|---|---|---|---|
| 2004年9月13日~9月17日 (5日間) |
東内科クリニック 看護師 5名 |
透析室看護ケア- 技術等の見学 |
透析室 |
4. 地域への教育活動等
(1) 県立日南医療連携セミナー
地域医療連携室主催で、3回開催した。対象は南那珂地区の医療従事者。
| 開催日時 | 内容 | 参加者数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 2005.5.24 第8回 | 「間違いだらけの心電図の勉強法(2)?不整脈編」 藤浦 芳丈(内科) | 135名 | 講堂 |
| 2005.10.4 第9回 | 「リスクマネジメントのABC―リスク感性を高めよう」 田中 茂子(看護科中央材料室師長) | 99名 | 講堂 |
| 2006.3.10 第10回 | 「胃瘻の構造とは」松田 俊太郎(外科) 「胃瘻のケア」 河野 穂波(看護科6西主任看護師) | 140名 | 講堂 |
(2) 呼吸生理と人工呼吸器に関する講義
| 講演 | 呼吸生理と人工呼吸器 |
|---|---|
| 講師 | 長田 直人(麻酔科) |
| 開催日 | 2005年8月6日 宮崎市・アズムホール |
(3) 思春期教育-命の大切さを考える-
| 講演 | 「性教育・命の大切さ」「性情報への対応」「生命の誕生」「性非行、性犯罪」 |
|---|---|
| 講師 | 門川 久子、中倉 輝子(看護科4東病棟、助産師) |
| 開催日時 | 対象 | 会場 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 2006.2.8 | 細田中学校 | 細田中学校 | 48名 |
| 2006.2.15 | 細田中学校 | 細田中学校 | 46名 |
| 2006.3.10 | 飫肥中学校 | 飫肥中学校 | 90名 |
| 2006.3.9 | 吾田中学校 | 吾田中学校 | 210名 |
| 2006.3.10 | 飫肥中学校 | 飫肥中学校 | 90名 |
(4) 衛星遠隔研修実践講座(看護ケア)
平成16年6月から衛星通信を利用した看護研修講座を開設した。不定期に行われる特別講座を院内全職員の集合教育に使用することもある。
開催日は原則として毎月第4木曜日、県南日南・串間医療圏の地域の病院にも呼びかけ、約50%が院外からの参加者であり、地域貢献に役立っていると考える。
| 開催日時 | 内容 | 参加者数(人) |
|---|---|---|
| 2005.4.28 | 「看護記録」 個人情報保護法とフォーカスチャーティング | 58 |
| 2005.5.26 | 「スキルアップⅠ」 知っておきたい 薬の知識薬のリスクマネジメント | 55 |
| 2005.6.23 | 「感染管理」 実例で学ぶ感染管理 ーベッドサイドケアにおける感染対策ー | 61 |
| 2005.7.28 | 「救急看護」 | 135 |
| 2005.8.25 | 「スキルアップ」 研究の活かし方 ー研究テーマの絞り込みの実際ー | 19 |
| 2005.9.8 | リスクマネジメント特別講座「個人情報保護法」 ~医療現場における留意点~ | 院内のみ30 |
| 2005.9.22 | 「臨床」緩和ケア」 ~東札幌病院の実践~ | 37 |
| 2005.10.27 | 「リスクマネジメント」 ヒヤリハットの実例と解説ー患者、家族指摘事例を中心にー | 77 |
| 2005.12.22 | 「糖尿病看護」~どこにでもいる糖尿病患者さんの一歩進んだ糖尿病ケア~ | 20 |
| 2006.1.26 | 「心理と病理」 リハビリメイクとは | 68 |
| 2006.3.23 | 「がん看護」 | 18 |
| 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/8 | 9/22 | 10/22 | 12/22 | 1/26 | 3/23 | |
| 3東・ICU | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 4東・NICU | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 4 西 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 5 東 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 西 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 6 東 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 6 西 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||
| 手術室 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 透析室 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 中 材 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 外 来 | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 看護部 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| その他 | |||||||||||
| 院 外 | 42 | 33 | 28 | 56 | 8 | / | 16 | 51 | 8 | 50 | 5 |
| 合 計 | 58 | 55 | 61 | 135 | 19 | 30 | 37 | 77 | 20 | 68 | 18 |
| 年間総数 | 578 | ||||||||||
* 11月・2月は希望参加者が少数のため、中止した
5. はまゆう会・糖尿病を学ぶ会
はまゆう会では、糖尿病に対する理解と自己管理の向上を目指して、毎年様々な年間行事を通じて、医師・栄養士・看護師との交流を行っている。
平成17年度の活動状況は下記の通りであるが、このほか「糖尿病を学ぶ会」にも同時に参加し、学習や交流を深めている。
※はまゆう会:糖尿病の患者さんに、糖尿病に対する関心を高めていただくために、平成2年7月に発足した「日南病院糖尿病友の会」の名称で会員数は21名。
| 年月日 | 行事 | 参加者 |
|---|---|---|
| 2005.4月 | 第16回はまゆう会総会 | 12名 |
| 2005.年3回 | はまゆう役員会 | 24名 |
| 2005.4月 | 糖尿病を学ぶ会総会・講演会 | 35名 |
| 2005.9月 | 糖尿病スタッフ研究会 | 43名 |
| 2005.10月 | 糖尿病歩こう会 | 14名 |
| 2005.11月 | 糖尿病糖尿週間日南串間大会 | 77名 |
| 2005.12月 | 糖尿病グランドゴルフ | 16名 |
| 2006.3月 | 糖尿病吹き矢挑戦 | 17名 |
6. 献血への協力
県立日南病院では、地域が必要とする安全性の高い血液を確保し、県民の皆様の健康と生命を守るため宮崎県赤十字血液センタ-が病院構内で実施する献血に積極的に協力している。
- 献血実施日 平成17年 5月24日
平成17年11月16日 - 献血受付者数 延70名
7. 県立日南病院祭
第7回県立日南病院祭を平成17年11月27日(日)に開催した。
今年も、病院職員だけでなく、入院患者、外来参加者、ボランティア、スタッフ等の約2,000名の参加者で賑わいました。
- 各コーナー
- 医療器械展示~X線装置など見学
- 検診・測定コーナー~血圧・血糖値・骨密度測定など簡単な健康状態検査
- 治療食を知ろう!
- フリーマーケット
- イベントコーナー
- 糖尿病について~血糖チェックや生活相談、正しい手洗いの仕方
- クリニカルパス展示
- 臓器移植に関するパネル展示
- 油津小学校スケッチ大会作品展
- 宮大医学生の医学展(解剖病理学展、患者さんの気持ち展、アロマでリラックス)
- 生き方上手~緩和ケア活動紹介・健康講座・眼圧・聴力検査
- NICUの紹介~リフロロジー分娩法
- ミクロの世界~組織・細胞標本展示
- 南睦会総合作品展
- 物産販売
- アトラクション
- 獅子舞奉納(天翔)
- シングアウト・キッズ(ダンス・コーラス)
- 日南カトリック園児(マツケンサンバ)
- 藤間流寿樹会(日本舞踊)
- 潮わらばー会(沖縄エイサー)
- ビブレフラ星倉飫肥(ハワイアンフラ)
- かすみバンド(バンド演奏)
- 県立日南病院音楽部(フルート・クラリネット演奏)
- ご協力いただいた方々
宮大学医学部学生、日南学園(看護学科・野球部)、日南看護専門学校、アトラクション参加の皆様、フレッシュマートキッチン、日南市社会教育課他
8. 各診療科等が協力した地域の催し、イベント等
平成17年度に各診療科が協力した地域の催しは次のとおりである。
【イベントへの当院職員の派遣】
- 「おっぱい相談会」 平成17年8月2日(火) 会場:宮崎市宮崎保健所
当院看護師2名
平成17年8月4日(木) 会場:都城市母子保健センター
当院看護師2名 - 「まちの保健室相談会」 平成17年6月25日(土) 会場:宮崎市カリーノ宮崎
当院看護師1名
平成17年7月17日(日) 会場:宮崎市カリーノ宮崎
当院看護師1名
平成18年1月15日(日) 会場:宮崎市カリーノ宮崎
当院看護師1名
【イベント時における急患等の搬入対応への協力依頼】
- 日露戦争・ポーツマス条約締結100周年記念国際シンポジウム
平成17年5月19日(木)~22日(日) - 油津港まつり2005
平成17年7月23日(土)~24日(日) - 日南市・那覇市姉妹都市交流バレーボール大会
平成17年7月31日(日) - 日南市・那覇市学童軟式野球選手権大会
平成17年8月20日(土)~21日(日) - 小村寿太郎候生誕150周年記念式典
平成17年9月26日(月) - 第28回飫肥城下まつり
平成17年10月15日(土)~16日(日) - 第10回油津堀川まつり
平成17年11月12日(土)~13日(日) - 第5回つわぶきハーフマラソン IN日南
平成17年11月20日(日) - 港あぶらつ朝市開催100回記念イベント
平成18年2月12日(日)
平成17年度(平成17年4月1日~平成18年3月31日)
平成17年度年報発刊に際して
平成12年末に最初の「宮崎県立日南病院年報」が平成11年度の年報として発刊され、柴田紘一郎前院長の巻頭言によれば、「20世紀まとめの節目の年を機に、日南病院活動の記録を今後、年度ごとに作成することにしました。自分たちの仕事の成果をまとめ、記録に残すとともに、これを職員間、部門間の情報交換の場として活用することは有意義だと考える次第です。そのことが自省にもなり、また将来の病院発展の足がかりとなると確信しています。」と述べておられます。
爾来年度ごとに年報が発刊され、21世紀における日南病院の歩みが記録に残されてきました。この間多くの職員が入れ替わりましたが、各年度の年報に目を通しますと、日南病院と地域医療の発展に貢献しようという職員各人の意気込みが感じられます。特に病院機能評価認定取得に向けての取り組みを通じて、職員の意識が次第に変革されてきたことが伺われます。
しかし一方、医療を取り巻く環境は年々加速度的に厳しさを増し、医療制度改革の名の下に猫の目のように変わる診療報酬の改訂や、卒後臨床研修の必修化による医師の偏在と、それによる大学医学部附属病院と地方病院の勤務医の激減が、当院の経営にも大きな影響をもたらしています。
とりわけ日南・串間医療圏においては、少子高齢化の現象が顕著に現れており、医療圏の総人口は毎年約800人ずつ減少しています。この流れの中で当院の入院患者数と病床稼働率も年々減少してきています。当院の常勤医師数も一時に比べ減少し、そのため特に夜間の救急体制に不備を生じており、他の医療圏に患者が流出している事態にもなっています。医師の欠員を補充し収益を生む医療スタッフを充実させようとしても、最大の医師供給源である宮崎大学医学部も医師不足に悩んでおり、他県の大学も県外に医師を派遣する余裕はありません。
「温故知新」という言葉があります。国語辞典によれば、昔のことを尋ね求めて、そこから新しい見解・知識を得ることと解釈されています。これはまた、過去のデータを基に新たな出発をするという意味にもとれます。平成17年度は当院が県の福祉保健部県立病院課に属していた最後の年度であり、今手にしておられる平成17年度の年報はその年度の記録であります。ご承知のように平成18年4月に宮崎県に於いても地方公営企業法の全部適用が実施され、病院局が発足して病院事業管理者(病院局長)の指導の下に県立病院の経営改善に取り組むことになりました。とりわけ当院は他院に比べこれまで最も大きな累積欠損金を生じており、最も周囲の状況が厳しい中で最も経営の健全化が求められています。
職員の皆様におかれましてはこの年報を熟読して頂き、ポジティブなデータばかりでなくネガティブなデータにも目を留め十分に分析して、それを改善するにはどうしたらよいかを職員一人一人が自分のこととして考えて頂きたいものと心から願っています。
最後に、年報の編纂にご尽力頂いた医療連携科の木佐貫医長と庶務係スタッフに深謝いたします。
平成18年10月 脇坂信一郎
第1章 病院の概要
1. 病院の概要
| 所在地 | 日南市木山1丁目9番5号 | |
|---|---|---|
| 開設年月日 | 昭和23年9月1日 | |
| 現施設新築年月日 | 平成10年2月24日 | |
| 診療科目 | 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、神経内科、麻酔科、精神科、心療内科 (計16診療科、リハビリテーション科は兼任、内心療内科・精神科は休診) |
|
| 許可病床数 | 一般336床、感染症4床、合計340床 | |
| 診療報酬 | 一般病棟入院基本料Ⅰ群入院基本料1 (2対1以上、平成16年4月1日から) |
|
| 施設の規模 | 土地 建物 駐車場 |
36,046.23㎡ 23,400.89㎡ 外来 283台 職員 233台 |
診療日案内
- 受付時間
新患(はじめての方) 午前8時30分から午前11時まで
再診(2回目以降の方) 午前8時30分から午前11時まで
※ 予約の方は、その曜日・時間に
但し、木曜日の皮膚科は午前8時30分から午前9時30分までの予約診療のみ
脳神経外科は、手術のための外来診療ができない場合あり - 急患はいつでも受け付け
- 土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休診
組織
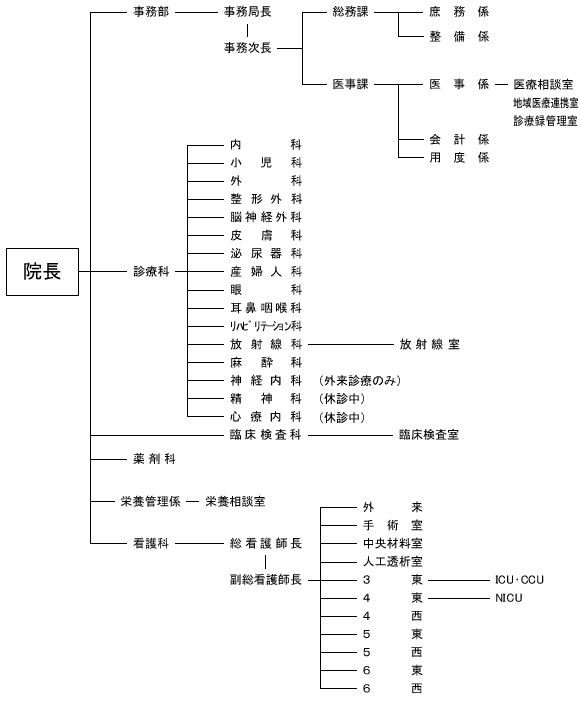
職員数
| [医療部門] | 71人 | |
|---|---|---|
| 医師 | 41人(臨床研修医9人含む) | |
| 薬剤師 | 7人 | |
| 放射線技師 | 8人 | |
| 臨床検査技師 | 9人 | |
| その他の医療技術者 | 6人 | |
| [看護部門] | 222人 | |
| 看護師 | 211人 | |
| 看護補助員 | 11人 | |
| [給食部門] | 15人 | |
| 管理栄養士 | 4人 | |
| 技術員 | 11人 | |
| [管理部門] | 17人 | |
| 事務員 | 15人 | |
| 技術員 | 2人 | |
| [合計] | 325人 | |
2. 病院事業の執行状況及び事業実績
当病院は、日南串間医療圏域における公的医療機関として、ICU(集中強化治療室)・CCU(冠動脈疾患集中治療室)・NICU(新生児集中治療室)の整備を行い、高度医療機器を充実し、地域社会に貢献する中核病院として質の高い医療サービスの確保に努めてきたところである。
経営状況は、まず収益では、入院患者数が前年度比で 6,346人減少したこともあり、入院収益は3,182,124,670円と前年度に比べ135,903,791円減少した。また、外来患者数は前年度比で10,845人減少したものの、外来収益は1,040,831,963円と前年度に比べ32,184,393円増加した。これにより医業収益は、4,509,861,980円と前年度に比べ105, 356,546円の減となった。
次に、費用については、医療器械の減価償却費が減少したものの、退職給与金の大幅な増加や災害拠点病院整備事業費が増加したため、医業費用は5,726,116,029円と前年度に比べ 37,404,783円の増となった。
その結果、経営収支の状況は、病院事業収益が前年度比で1.8 %減の5,356,308,931円に対して、病院事業費用が前年度比で0.5%増の6,218,016,501円となり、861,707,570円の当年度純損失を計上した。
- 患者の利用状況は、延入院患者数 99,155人、延外来患者数140,678人で、1日平均患者数を前年度と比較すると、入院患者数が17人減の272人、外来患者数が47人減の577人であった。
- 医療機器導入の状況は、一般撮影用CRシステムの更新等を行った。
(1) 患者の状況
| 区分 | 17年度 | 16年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 99,155人 | 105,501人 | △6,346人 |
| (一日当たり) | (272人) | (289人) | (17人) |
| 外来患者数 | 140,678人 | 151,523人 | △10,845人 |
| (一日当たり) | (577人) | (624人) | (△47人) |
| 病床利用率 | 79.9% | 85.0% | △5.1ポイント |
| 平均在院日数 | 20.0日 | 21.0日 | △1.0日 |
(2) 医療器械の整備状況
平成17年度は一般撮影用CRシステム、手術室用CR装置及び医療画像管理システムなど69件の整備を行った。
(3) 診療の状況
| 手術件数 | 3,608件 | ||
|---|---|---|---|
| 分娩件数 | 211件 | ||
| 解剖件数 | 2件 | ||
| 放射線件数 | 343,866件 | ||
| 人工透析件数 | 実患者数 延透析回数 |
68人 2,630回 |
|
| 人間ドッグ受診者数(日帰りのみ) | 75人 | ||
| 理学療法件数 | 延件数 一日当たり |
17,557件 72件 |
|
| 臨床検査件数 | 入院 外来 |
373,588件 788,400件 |
|
| 処方せん枚数 | ・外来処方せん 枚数 院外処方せん枚数 院外処方せん発行率 ・入院処方せん 総数 |
85,548枚(約353枚/日) 81,459枚 95.2% 24,499枚(約67枚/日) |
|
| 薬剤管理指導状況数 | ・注射処方せん枚数 ・服薬指導件数 |
31,286枚(約128枚/日) 734枚(月平均61.2件) |
|
| 給食の状況 | 延食数 一日当たり |
236,857食 649食 |
|
| (栄養指導件数) | 入院 | 個別 集団 |
1,544件 851件 |
| 外来 | 個別 集団 |
97件 82件 |
|
(4) 経営状況(決算の推移)一覧表
| 予算科目 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院事業収益 | 6,178,502 | 6,405,565 | 6,061,169 | 5,606,665 | 5,703,897 | 5,453,421 | 5,356,309 | ||
| 医業収益 | 4,970,444 | 5,289,057 | 5,085,648 | 4,693,711 | 4,717,676 | 4,615,219 | 4,509,862 | ||
| 入院収益 | 3,219,787 | 3,428,160 | 3,323,488 | 3,396,576 | 3,315,998 | 3,318,028 | 3,182,125 | ||
| 外来収益 | 1,491,482 | 1,599,004 | 1,483,336 | 1,016,242 | 1,105,391 | 1,008,648 | 1,040,832 | ||
| 一般会計負担金 | 110,827 | 113,137 | 140,078 | 137,232 | 152,933 | 157,325 | 170,499 | ||
| その他医業収益 | 148,348 | 148,756 | 138,746 | 143,661 | 143,354 | 131,218 | 116,406 | ||
| 医業外収益 | 1,208,058 | 1,110,325 | 975,521 | 912,954 | 986,221 | 838,202 | 846,447 | ||
| 一般会計負担金・補助金 | 1,105,157 | 1,099,349 | 971,536 | 909,274 | 942,271 | 828,181 | 834,140 | ||
| その他医業外収益 | 102,901 | 10,976 | 3,985 | 3,680 | 43,950 | 10,021 | 12,307 | ||
| 特別利益 | 0 | 6,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 病院事業費用 | 7,439,287 | 7,591,888 | 7,208,907 | 7,185,935 | 6,730,818 | 6,189,615 | 6,218,017 | ||
| 医業費用 | 6,809,188 | 6,963,372 | 6,612,880 | 6,637,058 | 6,209,125 | 5,688,712 | 5,726,116 | ||
| 医業外費用 | 630,099 | 628,516 | 596,027 | 548,877 | 521,693 | 500,903 | 491,901 | ||
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 収支差(当年度純利益) | -1,260,785 | -1,186,323 | -1,147,738 | -1,579,270 | -1,026,921 | -736,0194 | -861,708 | ||
| 償却前利益(非現金費用を控除) | 64,378 | 165,280 | 175,057 | -302,881 | 179,809 | 233,919 | -46,726 | ||
| 累積欠損金 | 4,441,765 | 5,628,088 | 6,775,826 | 8,355,096 | 9,382,017 | 10,118,211 | 10,979,918 | ||
| 一般会計からの繰入金合計 | 1,215,984 | 1,212,486 | 1,111,614 | 1,046,506 | 1,095,204 | 985,506 | 1,004,639 | ||
| 非現金費用 | 減価償却費 | 4,970,444 | 5,289,057 | 5,085,648 | 4,693,711 | 4,717,676 | 4,615,219 | 4,509,862 | |
| 資産減耗費 | 3,428,160 | 3,323,488 | 3,396,576 | 3,315,998 | 3,318,028 | 3,182,125 | |||
| 繰延勘定償却 | 1,208,058 | 1,110,325 | 975,521 | 912,954 | 986,221 | 838,202 | 846,447 | ||
| 計 | 1,325,163 | 1,351,603 | 1,322,795 | 1,276,389 | 1,206,730 | 970,113 | 814,982 | ||
3. 院内の主な行事
(1) 定例会
- 病院運営会議(毎月第1・第3月曜日 応接室)
- 経営改善検討委員会(年3回 講堂)
- 医局会(毎月第3水曜日 講堂)
- 代表者会議(毎月第4木曜日 講堂)
- 衛生遠隔研修(毎月第4木曜日 講堂)
- 臨床懇話会(毎月第3水曜日 講堂)
- 役職会(毎週水曜日 第1会議室)
- 院内感染症対策委員会(毎月第2木曜日 第1会議室)
- リスクマネージメント部会(毎月第2金曜日 第1会議室)
- 薬事委員会(毎奇数月第4水曜日 講堂)
- 診療材料検討委員会(年4回)第1会議室)
- 業務委託関係者連絡会議(偶数月第4金曜日 第1会議室)
- 師長会議(毎月第1・第3火曜日 看護科)
- 主任会(毎月第1金曜日 第2会議室)
- 教育部会議(毎月第2火曜日 第2会議室)
- 看護記録検討委員会(毎月第4木曜日 第2会議室)
(2) 主な行事
17年4月
- 辞令交付式(1日 講堂)
- 2005年「広島東洋カープ」サイン展(2月14日~1月31日 エントランスホール)
- 平成17年度当初予算及び平成17年度決算説明会(8日 県電ホール)
- 「病院機能評価の日」記念講演(19日 講堂)
- 平成17年度福祉保健部全体所属長会議(22日 県庁3号館)
- 日南地区官公庁連絡協議会(27日 ホテルシーズン日南)
17年5月
- 平成16年度決算ヒアリング(11日 県庁3号館)
- 広報編集委員会(12日 第1会議室)
- 「看護の日」ナイチンゲール像、花飾り(12日 エントランスホール)
- 南那珂地方連絡協議会(31日 ホテルシーズン)
- 監査事務局監査(31日~2日 第1会議室)
- 串間市国民健康保険病院落成式(21日 串間市民病院)
17年6月
- 日南・串間市政記者クラブ等との意見交換会(2日 管内)
- 県立病院あり方検討委員会(13日 県庁講堂)
- 監査委員監査(14日 第1会議室)
- 倫理委員会(21日 第1会議室)
- 医療事故防止対策委員会(22日 第1会議室)
- インシデント報告会(29 日 講堂)
- 七夕飾り(25日~7月7日 エントランスホール他)
- 消防訓練(7日~10日 院内)
- 全国自治体病院協議会九州地方会議(30日 別府市)
17年7月
- 「県立病院のあり方」説明会(7日 講堂)
- 地元選出県議会議員との意見交換会(13日 日南総合庁舎)
- 全国自治体病院協議会宮崎県支部総会(15日 宮崎市)
- 放射線業務従事者講習会(20日 講堂)
- 人権同和問題研修会幹部研修(20日 日南総合庁舎)
- 広報編集委員会(20日 第2会議室)
- 臨床研修病院(管理型)「第1回研修管理委員会」(21日 第1会議室)
- 全国公立病院連盟九州支部総会(28日 宮崎市)
- ふれあい看護体験2005(29日 院内)
- 勢井由美子氏「やすらぎの夕べ」コンサ-ト(29日 エントランスホール)
17年8月
- 3公立病院意見交換会(3日 串間市民病院)
- 平成17年度宮崎大学医学部・宮崎県連携推進協議会(5日 県庁3号館)
- 病院機能評価委員会(10日 講堂)
- 北郷町長・町議会議員不在者投票(18日 各病棟)
- 南睦会総会(26日 講堂)
- 臨床研修(管理型)募集者面接(27日 第1会議室)
- 平成18年度当初予算編成方針説明会(31日 県庁3号館)
17年9月
- 衆議院議員不在者投票(8日 各病棟)
- 救急の日(AED説明会 9日 講堂)
- 栄養管理委員会(12日 第一会議室)
- 第1回経営改善委員会(16日 講堂)
- 県議会生活福祉常任委員会決算審査委員会(30日 講堂)
- 「バイキング」昼食(29日 4階食堂)
- 4県立病院レクリエ-ション大会(3日 県運動公園)
- 消防設備点検(21日~26日 院内)
17年10月
- 第3回県立日南病院子供スケッチ大会(12日 院内)
- 接遇研修(17日 第1会議室)
- 医療監視(18日 講堂)
- 平成18年度当初予算要求総括ヒアリング(20日 県庁3号館)
- 女性専用外来「わかば」開設(21日 産婦人科隣専用室)
- 「バイキング」昼食(27日 5階食堂)
17年11月
- 第1回職業倫理講演会(8日 講堂)
- 第1回患者サ-ビス検討部会(9日 第1会議室)
- 県南地区放射線技師研修会(11日 講堂)
- 第1回救急委員会(15日 第2会議室)
- 第3回県立病院子供スケッチ大会表彰式(25日 応接室)
- 第7回県立日南病院祭(27日 院内)
- 院内接遇研修(28日、30日 第2会議室)
- 鳥インフルエンザ関係対策協議会(30日 日南保健所)
- クリーンアップ宮崎(13日 各地)
17年12月
- 第1回未収金対策等検討部会(1日 第2会議室)
- 「バイキング」昼食(1日 6階食堂)
- 「外来化学療法室」開設(12日 外来化学療法室)
- 放射線安全委員会(13日 第2会議室)
- 第2回患者サ-ビス検討部会(19日 第1会議室)
- 第2回経営改善委員会(20日 講堂)
- 南睦会交流会(16日 ホテルシーズン日南)
- 県立日南病院クリスマスコンサート(22日 エントランスホール)
- 総合防災訓練(26日 院内)
- 仕事納め式(28日 講堂)
18年1月
- 仕事始め式(4日 講堂)
- 新型インフルエンザ対策会議(17日 日南保健所)
- 日南地区官公庁連絡協議会(13日 北郷町)
- 第2回職業倫理講演会(24日 講堂)
- 日南市議会議員不在者投票(27日 各病棟)
18年2月
- 第2回未収金対策等検討部会(22日 第2会議室)
- TQM活動院内報告会(22日 講堂)
- 医療事故防止対策委員会(24日 講堂)
- 医療ガス保守点検(7日~11日)
18年3月
- 第2回救急委員会(1日 第2会議室)
- 3公立病院意見交換会(3日 講堂)
- 第1回費用削減等検討部会(8日 第1会議室)
- 第2回栄養管理委員会(13日 第2会議室)
- 電子カルテシステム導入委員会(13日 第1会議室)
- 第3回経営改善委員会(15日 講堂)
- 医療ガス安全管理委員会(17日 第2会議室)
- TQM活動成果県大会(20日 宮崎病院)
- 院内表彰式(院内顕彰委員会)(29日 応接室)
- 電子カルテシステムリハーサル(11日、25日)
- 消防設備点検(8日~12日 院内)
4. 院内各種組織
| 名称 | 構成員 | 目的 | 開催 回数 |
|---|---|---|---|
| 病院運営会議 | 院長、副院長、医局長、事務局長、事務次長、薬剤長、総看護師長 | 病院の管理運営の基本方針及び重要事項について審議する。 | 21 |
| 医局会 | 全ての医師 | 医師の連帯を図る。 | 10 |
| 代表者会議 | 院長、副院長、医局長、各診療科代表者、事務局長、事務次長、医事課長、薬剤長、総看護師長 | 各科相互の情報交換を行い連携を図るとともに、病院職員間の意思疎通を図る。 | 12 |
| 役職会 | 事務局長、事務次長、副総看護師長、リハビリ科等各部門科長・各係長 | 各職場の情報交換を行い連携を図る。 | 44 |
| 倫理委員会 | 院長、副院長、診療科医師、事務局長、総看護師長、院外の学識経験者 | 院内で行われる医療行為及び医学の研究が倫理的、社会的観点から推進されるよう、その内容を審査する。 | 1 |
| 院内顕彰委員会 | 病院運営会議と同じ | 院内職員及び団体が患者サービス及び院内活性化に顕著な活動、業績をあげたときに表彰を行う。 | 1 |
| 経営改善検討委員会 | 院長、副院長、診療科部長、医局長、総看護師長薬剤科他各部門 | 経営改善を図るための各種対策について審議する。 | 3 |
| 患者サービス検討部会 | 医師、看護科、各部門代表、事務部門 | 院内・院外環境の改善、外来患者の待ち時間短縮、職員の接遇研修等を検討する。 | 2 |
| 診療報酬請求等検討部会 | 医師、薬剤科、看護科、事務部門 | 請求漏れ防止策、査定減対策等の検討を行う。 | 1 |
| 費用節減等検討部会 | 医師、看護科、各部門代表、事務部門 | 材料費、経費等について費用節減策を検討し、病院経営の改善に資する。 | 1 |
| 未収金対策等検討部会 | 看護科、事務部門 | 未収金の発生防止対策をたてるとともに、発生した未収金の早期回収の諸方策を検討する。 | 2 |
| 広報編集委員会 | 診療科医師、事務次長、薬剤科、臨床検査科、看護科、栄養管理科、 庶務係長 | 地域住民に信頼され親しまれる医療機関を目指すとともに、地域医療レベルの向上に貢献するため広報について協議する。 | 2 |
| 外来ボランティア運営委員会 | 事務次長、副総看護師長、看護科、医事係 | ボランティア活動の場を提供することにより患者サービスの向上、病院のイメージアップ、地域に開かれた病院を目指す。 | 1 |
| 医療機器等機種選定委員会 | 院長、副院長、事務局長、事務次長、医事課長、用度係長、総看護師長、購入予定部門代表 | 医療機器等の適正な購入を図る(300万円以上)。 | 2 |
| 診療材料検討委員会 | 麻酔科、内科、外科、脳神経外科、放射線科医師、事務局長、副総看護師長、薬剤科、医事課長、用度係長、サプライセンター | 診療材料の採用等に関する事項を審議 し、適正な業務執行を図る。 | 3 |
| 院内感染症対策委員会 | 院長、副院長、診療科医師、臨床検査科、薬剤科、看護科、事務部門 | 院内における感染症をサーベランスし、院内感染防止を始めとする各種感染予防対策について協議実施を行う。 | 13 |
| 臨床検査委員会 | 診療科代表医師、臨床検査科、看護科、事務部関係者 | 臨床検査業務の院内での有効活用に関する協議を行う。 | 1 |
| 輸血療法委員会 | 診療科代表医師、臨床検査科、薬剤科、看護科、事務部関係者 | 輸血に関する事項を審議する。 | 3 |
| 放射線安全委員会 | 診療科医師、放射線科、看護科、事務部門 | 放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保する。 | 1 |
| 手術室運営委員会 | 各診療科代表、手術室看護師長 | 手術室の運営、改善及び手術(麻酔)の予定作成について検討する。 | 1 |
| 集中治療室運営委員会 | 集中治療室室長、診療科医師、集中治療室看護師長・主任看護師 | 集中治療室での患者管理が安全かつ適正に行うことについて検討する。 | 2 |
| 褥瘡対策委員会 | 皮膚科医師、副総看護師長、主任看護師、専門領域研修参加看護師、薬剤部、栄養管理科、医事係 | 適切な褥瘡予防対策をとり、発生を防止するとともに褥瘡対策の啓蒙活動を行い、院内教育を推進する。 | 11 |
| 栄養管理委員会 | 内科部長、外科・小児科医師、総看護師長、各病棟看護師長、看護補助員、事務部関係者、栄養管理科 | 栄養管理業務の円滑な運営を図るため、研究、協議し、意見を院長に具申する。 | 2 |
| 医療事故防止対策委員会 | 診療科部長・医長、臨床検査科医長、薬剤長、総看護師長、事務局長、医事課長 | 院内における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立する。 | 4 |
| リスクマネージメント部会 | 医師、事務次長、看護科、薬剤科、栄養管理科、臨床検査科、放射線科 | 医療事故防止対策を実効あるものにするため、事故の原因分析や事故防止の具体策等について調査・検討を行う。 | 11 |
| 医療ガス安全管理委員会 | 診療科医師、薬剤科、看護科、用度係長、整備係長 | 医療ガス設備の安全管理を図り、患者の安全を確保する。 | 1 |
| 入退院委員会 | 診療科医師、副総看護師長、看護科、会計係長、医事係 | 患者の入退院に関する事項を検討し、円滑な入退院ができるように検討・提言する。 | 2 |
| 診療録管理保管委員会 | 診療科医師、看護科、中央カルテ室、医事係 | カルテの管理に関し、法令等で定めるもののほか、必要な事項を定める。 | 0 |
| 地域医療連携委員会 | 診療科医師、薬剤科、看護科、医事係 | 地域医療の連携を推進することにより、患者サービスの向上に努める。 | 0 |
| 図書委員会 | 診療科医師、副総看護師長、薬剤科、臨床検査科、放射線科、リハビリテーション科、看護科、庶務・用度係長 | 図書室の適正な運営の充実を図って職員の資質向上に寄与する。 | 2 |
| 診療情報提供委員会 | 診療録管理室長、事務局長、事務次長、医事課長、薬剤長、医療相談室長、総看護師長、診療科医師 | 診療情報の提供に対する可否等の意見 を病院長に答申し、適切な診療情報提供を行う。 | 2 |
| 安全衛生委員会 | 院長、医局長、事務局長、事務次長、総看護師長、組合推薦委員、庶務係長 | 職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。 | 1 |
| 防災対策委員会 | 診療科医師、事務局長、総看護師長、事務次長、薬剤長、検査科技師長、放射線科主任、リハビリテーション科主査、医事課長、栄養管理科主任、事務部各係長 | 防災知識の向上と訓練を通じて、職員、患者の安全を確保する。 | 1 |
| 薬事委員会 | 副院長、診療科代表医師、事務局長、薬剤長、総看護師長、医事課長 | 医薬品の適正かつ効率的な管理運営を図る。 | 6 |
| 治験審査委員会 | 副院長、内科部長、外科部長、整形外科部長、産婦人科部長、医局長、事務局長、薬剤長、総看護師長、放射線科技師長、臨床検査科技師長、外部委員 | 医薬品の臨床試験の実施可否等を審議する。 | 0 |
| 救急委員会 | 外科・内科・脳神経外科・小児科・整形外科医師、地域連携、副総看護師長、副薬剤長、検査科技師長、放射線科技師長、事務次長 | 県立日南病院救急医療運営要綱に基づく県立日南病院の救急医療の円滑な運営と適正な管理を図る。 | 2 |
| 教育研修委員会 | 院長、副医局長、事務次長、薬剤長、副総看護師長、臨床検査科技師長、放射線科技師長 | 職員の資質の向上を図り、良質な医療の提供、患者サービスの向上に資する。 | 3 |
| 電子カルテシステム導入推進委員会 | 院長、副院長、産婦人科・内科・外科医師、事務局長、外各部門代表9名 | 「医療の質の向上」、「病院管理運営の効率化」、「患者サービスの向上」等を目的とし、効率的かつ効果的な電子カルテシステムの導入に伴う諸問題について検討を行う。 | 1 |
| 病院機能評価委員会 | 院長、副院長、院内各部門代表者 | (財)日本医療機能評価機構が行う病院機能評価認定証の取得を通じて病院機能の向上に資する。 | 1 |
| 献立検討委員会 | 栄養士、調理師 | 献立内容と食器等について検討する。 | 12 |
| サプライ業務連絡会議 | 副総看護師長、手術室師長、中央材料室師長、用度係長、診療材料担当、看護補助員、サプライセンター主任 | 診療材料の院内物流業務に係る日常の問題点の協議、部署間の連絡を行う。 | 2 |
| 地域がん拠点病院運営委員会 | 外科医長、内科医長、薬剤長、診療録管理室長、栄養管理科士長、放射線科医長、総看護師長、臨床検査科医長、緩和ケアチーム(師長)、事務局長、医事課長、医事係、地域連携室、ニチイ学館 | 地域住民が日常生活圏で質の高い全人的ながん医療を受けることができる体制を整備し、拠点病院の運営について検討する。 | 3 |
| 師長会議 | 総看護師長、副総看護師長、看護師長 | 看護管理上の施策・方針を協議し決定する。看護の質向上を目差して病棟等の運営管理の共通理解を深める。 | 23 |
| 主任会議 | 総看護師長、主任看護師 | 師長を補佐し主任としてどうかかわっていくか等、情報交換し検討する。看護実践のリーダーとして質向上を目差す。 | 11 |
| 教育部会議 | 副総看護師長、看護師長、主任看護師 | 看護職員の資質の向上と業務に対する意欲の高揚を図る。業務内容の充実を図るための教育・研修を計画、実施する。 | 11 |
| 看護業務改善委員会 | 看護師長、主任看護師、各部署看護師 | 業務の改善、看護サービスにつながる事柄を協議・検討し、見直した結果を看護科等に答申する。 | 5 |
| 臨地実習指導者会 | 副総看護師長、臨床指導者、各学校教務 | 看護学生の臨床指導の向上及び指導者の研鑽に努める。各学校の実習計画の把握と反省会を通し、実習上の問題の解決を図る。看護基準・指導要領の見直しを継続 | 11 |
| 看護基準・手順委員会 | 副総看護師長、看護師長 主任看護師、看護師 | 看護に必要な基本的な手順・基準を検討するとともに見直しや、必要とする手順・基準の作成を行う。 | 4 |
| 看護記録推進委員会 | 副総看護師長、看護師長主任看護師、各部署看護師 | 看護記録のあり方を検討し、記録の充実を図り看護の質の向上に努める。 | 11 |
| 看護研究委員会 | 副総看護師長、教育担当師長、教育担当主任看護師、看護師 | 看護現場の問題を研究的視点で見ることができ、創造的に解決できる。病院全体の問題としてとらえることができる。 | 8 |
| 接遇委員会 | 副総看護師長、看護師長、主任看護師、看護師 | 看護の視点で接遇をとらえ、あたたかく良質な看護サービスが提供できるように、実践の指導的役割ができる。 | 4 |
| 感染看護研究会 (ICT) | 副総看護師長、看護師長、専門領域研修参加看護師 | 感染看護研修で学んだ知識・技能を実践の場で生かすことができる。 サーベランス活動を通して、院内感染対策活動を推進する。 | 11 |
| 緩和ケア看護研究会 | 副総看護師長、看護師長、主任看護師、専門領域研修参加看護師 | 職種間の連携をとり、情報の収集や啓蒙を行うとともに緩和ケアにおける質の向上を図る。 | 11 |
| 救急看護研究会 | 副総看護師長、専門領域研修参加看護師 | 救急看護に関する専門的な知識・技術を看護実践に活かし、救急看護の質の向上を図る。 | 11 |
| 糖尿病看護研究会 | 副総看護師長、看護師長、専門領域研修参加看護師 | 糖尿病看護に関する専門的な知識を活かし指導的役割を発揮する。糖尿病患者のQORの向上のための実践における推進者となる。 | 11 |
| リエゾン精神看護研究会 | 副総看護師長、看護師長、専門領域研修参加看護師 | 精神看護の知識・技術をその他の領域の看護に適用し、スタッフ間の連携を図り質の高い看護サービスを提供する。 | 11 |
| がん化学療法研究会 | 副総看護師長、専門領域研修参加看護師 | がん化学療法について専門的な知識を活かしスタッフに提供する。がん化学療法看護チームの活動を通じてがん患者やその家族に対して、質の高い看護が提供できる。 | 2006.1月~ 研修開始 |
| パス委員会 | 副総看護師長、看護師長、看護師 | チーム医療による質の高い医療を効率的に提供し、患者満足度を高めるために、パス(クリティカルパス・クリニカルパス)の導入推進、円滑な運用、職種間の調整を行う。 | 8 |
5. 病院機能評価認定更新に向けての取り組み
平成14年度から(財)日本医療機能評価機構の行う病院機能評価事業に取り組み、多くの改善活動をおこなってきた。平成15年5月19日に認定留保通知受領、平成16年3月30日の再審査受審を経て、平成16年4月19日に認定証(バージョン3.1,一般病院種別B)発行が決定された。
当院では認定証交付日である4月19日を「病院機能評価の日」と定めて、毎年機能評価関連の行事を実施していくこととなり、最初の記念行事をおこなった。
しかし、平成17年度には人事異動に伴い機能評価に関わった事務系職員がほとんどすべて当院を去ったこともあり、委員会開催も1回のみと、認定更新に向けての取り組みは停滞したといわざるを得ない。平成20年度には更新審査を受けることになる。次回受審となるバージョン5もしくは6のクリアを目指して、日南病院全体の水準をより高め、理念を実現すべく病院に勤務する(委託、臨時も含む)職員全員が一丸となって取り組んでいく姿勢が重要である。次期更新までにのこされた時間は少なく、改善に長期間を要すると思われる項目もあるため、次年度以降再度部門毎の認定更新に向けての取り組みが求められる。
【病院機能評価の日記念行事】
日時:4月19日(火)
場所:講堂
内容:報告「2004年認定病院の集い報告」木佐貫 篤(臨床検査科)
講演:「評価基準version5について」山口 もと代氏(前宮崎県看護協会会長)
参加者:84名(医局9名、看護46名、薬剤6名、検査9名、放射線5名、事務局9名)
| 回数 | 開催日・場所 | 主な討議内容 |
|---|---|---|
| 第38回 | 8月10日(水) 16:00~16:40 |
今年度の委員、規約について、病院機能評価の日(4月19日)報告、次回認定更新に向けて(認定基準version5)の問題点抽出、他 |
【職員オリエンテーションにおける機能評価説明会】
4月新規採用及び転入職員に対して、病院機能評価への基本的な認識を持っていただくために、職員オリエンテーション時に機能評価について説明を行った。
開催日:4月6日(水)14:00~(約40分)
場所:講堂
担当:木佐貫 篤(機能評価委・副委員長)
内容:機能評価とは何か、当院の取り組み(問題点、対応対策)、今後の対応、など
6. 感染症対策への取り組み
院内感染対策として、毎月第3木曜日に院長を委員長とする院内感染対策委員会を開催し、細菌の検出状況や環境調査の定期報告などを行い、適切な感染対策の実施に取り組んでいる.平成17年度は、平成16年度に引き続きSARS対策の検討をすすめるとともに、予想される新型インフルエンザへの対応についても検討を行った。また、ICTチームを立ち上げ、毎月第2木曜日に木佐貫医師をリーダーに10名のメンバーでMRSA患者の院内ラウンドを開始した。
(平成17年度に実施した主な活動)
- SARS対策マニュアル等完成
- 院内感染対策研修会(7月1日実施)参加者70名
- 染症週報による院内職員への感染症関連情報提供
- 院内汚染(針刺し)事故マニュアル完成配布
- 転入及び新規採用職員のツベルクリン反応検査実施
- 転入及び新規採用職員の肝炎抗体検査及びHBs抗体陰性者へのワクチン接種
- 職員(希望者)へのインフルエンザ予防接種実施(11月)
- 手術部とICU間の1足制導入
- 新型インフルエンザ患者受け入れ県立日南病院は32床決定
- 全自動洗浄機での最終すすぎをRO水から水道水に変更決定
- 新型インフルエンザ対策模擬訓練(3月17日)
委員会実施内容を以下に示す。
【 院内ICT の活動 】
院内感染対策の充実を目的として、ICT(infection control team 感染制御チーム)の設置が2005年4月の院内感染対策委員会にて承認された。ICTは、医師2名、看護師6名、薬剤師・臨床検査技師・事務各1名からなり、毎月第2木曜日にミーティングと院内ラウンドを実施した。またラウンド内容は毎月の院内感染対策委員会へ報告した。
平成 17 年度は、MRSA保有患者さんを主なラウンド対象として、適切な隔離、感染対策が行われているかどうかのチェックを行った。その他ICTが取り組んだ主な活動を下記に示す。
- MRSA発生報告、隔離解除報告の手順確立
- MRSA隔離解除報告用紙の改訂
- 看護科感染看護グループとの連携推進
- 長期入院患者さんへのインフルエンザワクチン接種
- トイレへのペーパータオル設置への取り組み
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| H.17.4.21 | 院内感染対策内規の改正、感染症月報報告、インフルエンザ検査状況、感染症週報に委員会報告を掲載することとした、SARS対策マニュアル等の早期完成を目指す、7月に研修会を行う、ICT(感染対策チーム)を立ち上げ月1回ラウンドする |
| H.17.5.19 | 感染症月報報告、SARS対策マニュアル等を最終チェック後配布する、ICTのラウンドを第2木曜の午後行う、7月1日に院内感染対策研修会を行う、新規採用者と転入者を対象に肝炎ウイルス検査の採血を行った |
| H.17.6.16 | 感染症月報報告、感染研修会7月1日に決定、SARSと針差し事故マニュアル6月末完成予定、ツベルクリン反応検査とB型肝炎ワクチン接種が重ならないようにする |
| H.17.7.21 | 感染症月報報告、7月14日の第1回ICTラウンドの報告 |
| H.17.7.1 | 院内感染対策勉強会(参加者70名) |
| H.17.8.18 | 感染症月報報告、8月ICT活動報告、感染症患者隔離解除報告書の様式改訂、院内感染対策に関するアンケート全国調査への回答承認 |
| H.17.9.15 | 感染症月報報告、9月ICT活動報告、SARS疑い検査対応のためのダクト工事を認め病院側にお願いする |
| H.17.10.20 | 感染症月報報告、10月ICT活動報告、インフルエンザの予防接種について(11月21日22日実施)、針刺し事故マニュアル配布予定、洗浄仕上げをRO水から原水に変更する試行期間3ケ月程度承認 |
| H.17.11.10 | 感染症月報報告、手術部とICU間の1足制導入を手術室運営委員会で決定する |
| H.17.12.8 | 感染症月報報告、ICT11月活動報告、新型インフルエンザ対応最大19名タミフル備蓄は100cap確保しておく、長期入院患者へのインフルエンザワクチン接種12月下旬に実施する、救急センターでのタミフル処方は3日分とする |
| H.17.12.20 | 新型インフルエンザ対応について、県立日南病院は19床受け入れで最大32床までとした。南那珂地区で135床を目標とした 串間市民病院45床、国保中部病院58床 |
| H.18.1.19 | 感染症月報報告、ICT1月活動報告、インフルエンザ検査状況新型インフルエンザに関する協議報告県立日南病院32床、中部58床、串間市民45床 合計135床目標 |
| H.18.2.16 | 感染症月報報告、ICT2月活動報告、インフルエンザ検査状況、全自動洗浄機での最終すすぎをRO水から水道水に変更することを了承した、滅菌テストシステムの不備の報告 |
| H.18.3.16 | 感染月報報告、ICT3月活動報告、院内トイレペーパータオル設置要望委員会では承認したが、病院へ要望する、新型インフルエンザ対策の模擬訓練の実施(3月17日) |
7. 院内事故防止への取り組み
医療事故を未然に防ぎ質の高い医療を目指すために、医療事故防止対策委員会、リスクマネジメント部会が年度を通して活動を行い、収集されたヒヤリハット事例の原因分析・防止対策及び体制の改善を図った。その他、主な活動は次の通り。
- 職員対象の研修を下記テーマで1回実施した。
- 平成17年6月29日 リスクマネジメント研修会
各部門よりインシデント事例の報告
- 平成17年6月29日 リスクマネジメント研修会
- 部会は、8月をのぞいて毎月開催した。
8. 院外処方せんの発行と薬剤管理指導業務への取り組み
院外処方せんの発行状況
院外処方せんの発行(医薬分業)は、「かかりつけ薬局」で外来患者の服薬指導を行い、薬歴を一元管理することにより、薬剤の重複投与防止、副作用発現の把握、適正な服用の確保を図るため行われているものである。
本院では、平成13年10月から院外処方せんの発行を開始しており、発行状況は次のとおりである。
| 総数 | 院外処方枚数 | (発行率) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成15年度 | 107,291枚 | 103,381枚 | (96.4%) | 約425枚/日 |
| 平成16年度 | 94,679枚 | 90,773枚 | (95.9%) | 約373枚/日 |
| 平成17年度 | 85,548枚 | 81,459枚 | (95.2%) | 約353枚/日 |
薬剤管理指導業務の状況
薬剤管理指導業務は、患者への適切な薬物療法推進の観点から、院内各部門への医薬品情報を積極的に提供するとともに、入院患者を対象に、注射処方せんによる患者一人ごとに注射薬のセット払出を行い、薬歴管理、服薬指導などの業務を行うことにより、患者サービスの向上、医薬品の適正使用を図るものである。
本院では、院外処方せん発行後に業務を開始し、現在、実施対象患者の拡大に努めているところであり、実施状況は、次のとおりである。
服薬指導件数
| 平成15年度 | 711件 | (59.0件/月) |
|---|---|---|
| 平成16年度 | 611件 | (50.9件/月) |
| 平成17年度 | 734件 | (61.2件/月) |
指導対象
- 退院処方の服薬指導(全病棟)
- 6西病棟:糖尿病患者教育、毎月1回クリニカルパスによる集団服薬指導
- 3東病棟:眼科術後患者の服薬指導
患者個人毎の注射セット出し
| 平成15年度 | 29,490枚 | (約120枚/日) |
|---|---|---|
| 平成16年度 | 33,820枚 | (約139枚/日) |
| 平成17年度 | 31,286枚 | (約128枚/日) |
9.クリニカルパスへの取り組み
医療の質向上、患者さんの満足度向上のために、多くの病院で「クリティカル(クリニカル)パス」を導入する動きが活発化している。当院でもパスを導入する疾患が増えてきており、医療の質の向上と患者さんの満足度を高める一助となっている。
平成18年3月現在、当院で作成利用されているパスは10診療科72種類と昨年同期に比べてさらに増加した。今後電子カルテ導入に伴う電子化をすすめていくことが必要となる。
| 診療科 | 種類 |
|---|---|
| 内 科(9) | 心臓カテーテル検査、PTCA、ペースメーカー電池交換、シャント造設術、透析導入、ペースメーカー植込み術、HOT導入、糖尿病教育、CAG検査 |
| 小児科(2) | 胃腸炎、肺炎・気管支炎 |
| 外 科(7) | ヘルニア根治術(成人)、ヘルニア根治術(小児)、PEG造設、胃粘膜切除術(EMR)、乳房切除術、幽門側胃切除術、腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| 整形外科(9) | 大腿骨頸部・転子部骨折(手術前、手術後)、アキレス腱断裂再建術、変形性股関節術(寛骨臼球状回転骨切術、大腿骨外反骨切術)、抜釘術(変形性股関節症、一般整形)、踵骨骨折、足関節骨折 |
| 脳神経外科 (2) | 慢性硬膜下血腫除去術、脳血管造影(アンギオ) |
| 泌尿器科(3) | 経尿道的前立腺切除術、経尿道的膀胱内切除術、前立腺生検 |
| 産婦人科 (31) | 開腹手術、膣式子宮脱手術、円錐切除術、子宮内容除去術、化学療法*、経膣分娩*、帝王切開術*、新生児、切迫流産、異常妊娠、双胎妊娠、妊娠中毒症、妊娠悪阻、頚管縫縮術、光線療法、呼吸障害児、低血糖児 |
| 眼 科(1) | 白内障 |
| 耳鼻咽喉科 (7) | 喉頭手術、扁桃摘出術、アデノイド切除・扁桃摘出術、鼓室形成術A、鼓膜チューブ留置術、鼻・副鼻腔手術、頭頸部手術 |
| 放射線科(1) | アンギオTAE |
| (合 計) | 72種類 |
*バリエーションあり(パス委員会まとめ)
これまでパス普及・利用促進に大きな役割を果たしてきた「クリニカルパス研究会」(平成14年秋設立、世話人10名)にかわり、平成17年度にパス委員会が設立され、同委員会主導でパス大会を始めとするパスへの取り組みが行われた。
平成18年度5月の電子カルテ導入を見据えて、平成17年12月よりパス基本部会ではパス作成基準、使用基準の改訂改定に取り組み、平成18年2月のパス大会で新しい作成基準を発表することが出来た。
また17年度は前年度に引き続き、医療マネジメント学会での演題発表1件(11月 福岡)、パス展示4件(6月 福岡、11月 福岡)及び宮崎医療連携研究会・地域クリニカルパス大会での発表(5月 宮崎)なども行い、院外学会活動にも積極的に取り組んだ。
| 日時 | テーマ | 発表者 | 参加総数 | 医 | 看 | 薬 | 栄 | 検放 | 事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11回パス研 05年5月11日 |
パスへの取り組み 鼠径ヘルニアパス |
木佐貫 篤医 長(病理) 松田俊太郎副医長(外科) 阿比留知子看護師(4西) |
43 | 8 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 第1回パス大会 05年11月1日 |
大腿骨頸部骨折パスver.9 気管支鏡パス |
有馬 沙智看護師(5東) 今津 善史医 師(内科) 河野 英梨看護師(6東) |
53 | 7 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 第2回パス大会 06年2月7日 |
新しいパス作成基準と電子カルテにおけるパス 新しい作成基準に準じたパスの実例 「鼠径ヘルニア」 |
木佐貫 篤医 長(病理) 阿比留知子看護師(4西) |
57 (4) |
6 | 38 | 3 | 1 | 3 | 1 |
出席者 医:医師 看:看護師 薬:薬剤師 栄:栄養士 検放:臨床検査・放射線技師 事:事務
( )内は院外からの参加者数
(院内外における活動など)
- 2005年 5月20日 第4回宮崎医療連携研究会・第1回地域クリニカルパス大会(宮崎市)
発表 阿比留知子「鼠径ヘルニアパス(PHS法) - 2005年 6月24-25日 第7回医療マネジメント学会学術総会(福岡市)
パス展示 竹中美香「扁桃摘出術」 荒川 志保「腹腔下胆嚢摘出術」
池田芳江「婦人科開腹術」 - 2005年10月29日 第4回医療マネジメント学会九州山口連合大会(福岡市)
発表・パス展示 阿比留知子「成人鼠径ヘルニア根治術」 - 2005年11月27日 県立日南病院祭
パスの概要説明とパス展示(扁桃摘出術、成人鼠径ヘルニア根治術)
10.その他の患者サービスへの取り組み
(1) みなさんのご意見への回答
当院では、当院に対する患者さんや家族の皆さんの意見や要望等を医療の提供、患者サービスに反映させることによって、患者本位の病院運営に資することを目的として、平成14年10月から院内7カ所に投書箱(平成16年8月から「ご意見箱」に名称を変更)を設置している。
平成17年度のご意見の件数は下記のとおりであるが、平成16年12月からは、ご意見等に対する回答を院内に掲示(2ヶ所)するとともに当院ホームページにも掲載している。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9件 | 12件 | 28件 | 8件 | 20件 | 7件 | 14件 | 16件 | 10件 | 11件 | 16件 | 23件 | 174件 |
(2) 外来ボランティアについて
本病院における患者サービスの充実を図るため、外来ボランティアの導入を行っている。
ボランティアに活動の場を提供することにより、患者サービスの向上、病院のイメージアップ、地域にひらかれた病院を目指すこと等を目的に実施している。
| ボランティアの人数 | 1人 |
|---|---|
| ボランティアの導入日時 | 平成13年7月16日から |
| 活動日時 | 月曜日から金曜日の午前中 |
| 主な活動内容 | エントランスホール周辺での患者さんの受付手続きの介助や診療科への案内 体の不自由なお年寄り等の車椅子乗降、移動の介助等 |
(3) 栄養管理科における患者サービス
栄養管理科は、入院患者さんの一日も早い回復のため、様々な創意工夫を懲らし患者さんに食を楽しんでいただくとともに食を通じて治療に関わっている。
| 適時適温給食 | 暖かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で患者さんの元に食事を届けるため保温・保冷配膳車を使っている。 |
|---|---|
| 選択食 | 毎週水曜日と金曜日は選択食の日とし、朝食と昼食についてそれぞれ2種類のメニューからどちらかを選んでいただけることになっている。 |
| 糖尿病教室 | 毎週木曜日、午後2時から3時まで、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、健康運動指導士が糖尿病についてわかりやすく説明している。 |
| バイキング | 当院としては初めての試みで、9/27、10/27、12/1に各階食堂で実施。しっかり選んで楽しく食べることを目的に実施した。 |
(4) 院内イベント
入院患者の生活に変化を持たせ、より快適な入院生活を送ってもらうために、次の企画を実施した。
| イベント内容 | 開催日 | 備考 |
|---|---|---|
| こどもスケッチ大会 | 17.10.12 | 西側庭園 油津小学校66名参加 |
| ふれあい看護体験の日 | 17.7.29 | 病棟 学生25名参加 |
| 「やすらぎの夕べ」コンサート (勢井由美子氏) | 17.7.29 | エントランスホール 患者・家族等 約100名参加 |
| 第7回県立日南病院祭 | 17.11.27 | エントランスホール 患者・家族等 約2,000名参加 |
| 南睦会文化祭 | 17.11.27 | 第2会議室 |
| クリスマスコンサート (日南学園合唱部、当院合唱部、職員家族) | 17.12.22 | エントランスホール 患者・家族等 約200名参加 |
(5) エントランスホール等の各種展示
| 展示内容 | 展示期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 2005年「広島東洋カープ」サイン展 | 17.2.14~ 18.1.31 | |
| 「看護の日」ナイチンゲール像、花飾り | 17.5.12 | 看護自治会主催 |
| 七夕飾り | 17.6.20~17.7.7 | 栄養管理科(短冊236枚) |
| こどもスケッチ大会展 | 17.11.27~17.12.9 | 油津小学校児童生徒の 皆さんの優秀作品36点を展示 |
| 「宝船」七福神みこし展示 | 18.1.4~18.1.31 | 宮崎大学医学部学生 |
| 「患者さんの気持ち」特別展 | 17.11.28~17.12.9 | 宮崎大学医学部学生 |
| 2006年「広島東洋カープ」サイン展 | 18.2.13~ |
(6) 院内テレビによる案内
外来・入院患者さん及び来訪者に、当院の様々な情報を提供する目的で院内テレビによる案内を行っている。主な内容は、病院・診療案内、糖尿病教室のお知らせ、今週の献立一覧、院内イベント案内等である。
11. 経費節減への取り組み
費用節減の方策等を検討し、各部署で業務の改善や見直しを実施するために、経営改善検討委員会に費用節減等検討部会が設置され、次のような活動を行っている。
- 各職員の費用節減に対する意識啓発を行う。
- 部会メンバーを中心に、各部署で費用削減策の取り組み目標を立て、実践活動を実行する。
- 各職員から費用節減のアイデアが日常的に出るような環境づくりを行う。
また、17年度の主な費用節減事例は、次のとおりである。
- 診療材料・消耗品等の見直し(手術室)…手術用綿布再生使用を全面ディスポ使用に切り替えた。また、縫合針や手術用ガウンの納入業者を変更した。さらに、マスクなどは同等品で安価な物品に変更した。
- 業務の改善、使用材料等の見直し等(中央材料室)…一次洗浄を中央材料室に集中化することで、各部署の洗浄時間を削減した。また、洗浄・消毒する診療材料(酸素マスク、ネブライザー蛇管など)を増やし再利用に努めた。さらに、全自動洗浄機の最終すすぎを水道水に変更した。(滅菌上問題なし)
- 業務委託の見直し(臨床検査科室)…検査機器の更新に伴い、検査試薬を同等品で競争入札とした。また、検査項目の院内検査へに一部変更を行い、外注検査項目を見直した。
- 電力入札の実施(整備係)…電力小売の自由化対象になったことにより、電力入札を実施した。使用電力量は増加したものの、単価が下がったため、使用料金は減額となった。
- 4県立病院による医薬品の共同購入の実施…各病院で個別に価格交渉をしていたが、平成17年度から本課一括による共同購入方式とした。
- 委託在庫の納入価格交渉の実施…価格交渉を行い、全体的に納入価格を下げた。
- 印刷関係(啓発活動)…両面コピーや院内印刷の推進を図った。
12. 未収金対策への取り組み
個人負担分の医業未収金は増加傾向であり、督促状や催告状の送付、臨戸訪問による徴収をおこなっている。
このような厳しい状況下、平成17年度は、未収金対策部会を2回開催し、発生防止策や早期回収の方策を検討し、院内職員が連携して未収金対策に取り組んでいるところである。
平成16年度から未収金徴収員を配置し臨戸訪問、未収患者実態調査等による未収金徴収業務を実施している。
13. 褥瘡対策への取り組み
院内の褥瘡患者発生の予防と早期治療を目標に、毎月第4金曜日に褥瘡対策委員会を開催し活動を行った。
主な活動としては、次のとおり
- 毎月の状況報告書の作成
- 啓蒙活動として毎月「ミルミルすきん」の発行し、情報を提供
- 集合教育...テーマ「褥瘡の診断と治療」
講師:皮膚科 長嶺医長 11月25日
参加者 30名 - 体圧分散用具(ソフトナース)14枚購入
- 現在の各フロア対策委員1名から平成18年度より各病棟委員を1名選出へ変更
14.緩和ケアへの取り組み
宮崎県地域がん診療拠点病院指定に伴い、緩和ケアチームとして多職種とのチームと共に活動した。
- 定例会
毎月会議を開催:行事の計画、研修の報告、反省会、事例検討会などおこなった。 - 講演会の開催
9月21日県立看護大 遠藤恵美子教授:「マーガレットニューマンの看護理論」について地域の医療機関にも「研修会の誘い」を発行し、院内・院外から参加が53名であった。 - 施設見学
鹿児島 堂園メデカルクリニック:看護師4名 薬剤士1名 管理栄養士1名参加
「死の準備教育」のパンフレットを活用して4西病棟で実践している。 - 研修会参加
- 日本死の臨床研究会:山口県 11月12~13日 看護師4名 管理栄養士1名
- 日本がん看護研究会 2月11~12日 看護師1名 福岡県九州癌センター主催
- 関紙発行
「ほっとぴあ」2回発行 (6月・3月) - 病院祭への参加
- ミニ講演会 Dr市成の乳癌について
- 緩和食展示
- ミニ講演会 癌の体験者の話
- 書物の紹介
- 鎮痛薬について資料展示
- イメージ療法の体験
- お茶会(抹茶とお菓子の提供)
- 「患者様と家族の方の会」の継続
- 毎週水曜日16時~18時まで当番制にて来院される患者、家族の方、院外よりの訪問者の対応にあたった。
- 家族会ノートを作成しチームの連絡、情報交換を行った。
- 家族会の内容:談話・医療相談・在宅への相談・お茶会(抹茶・菓子提供)
イメージ療法も取り入れた。 - お話ボランティアの協力があった。
- ボランティア活動
病棟訪問、病棟より依頼のあった患者・家族の方のケアにあたった。
外泊・在宅を訪問・電話訪問で支援した。 - TQM活動報告発表
題名「緩和ケアチーム1年間の活動「家族会」から見えてきたもの」を発表した - 南那珂在宅ケア研究会
事例発表「S状結腸癌のターミナル期で訪問看護を利用し24日間の在宅療養ができた事例」「患者様と家族の方の会」の紹介を行った。
15. 救急看護への取り組み
過去2年間の活動(院内BLS研修の実施と救急カート統一)を通して、日南病院における救急看護の基盤作りができたと考える。そこで17年度は災害看護にも活動を広げ、よりよい救急看護の実践に向けて新たな取り組みを行った。また、過去の実績を評価していただき、レサシアンを1体購入できたため、活動がよりスムーズにできるようになった。
主な活動内容は以下のとおりである
- 宮崎県総合防災訓練参加:5月29日 串間市 2名
- 1年目研修指導(救急看護について:10月28日 12名)
- 2年目研修指導(救急看護について:6月30日 24名)
- 院内AED研修実施:6東・西
- 洋上慣熟訓練参加:9月17日 2名
- 医師会AED指導者養成講習会参加:9月25日 1名
- 院内BLS研修実施:10月17日
- 県立宮崎病院 災害訓練見学:11月5日 1名
- 災害看護研修参加:看護協会 12月3日・4日
- 救急カートのラウンド:部署のチェック状況がかなり充実したため、半年に1回 のラウンドとし、全部署のラウンドを行った。
16.糖尿病看護の取り組み
糖尿病についての理解を深め、専門知識を生かし糖尿病患者へ統一した看護を提供 する。また県立日南病院における糖尿病看護の指導的役割を果たすことを目標に、毎月第4火曜日に糖尿病看護研究会を開催した。
主な活動は次のとおり
- 糖尿病教育入院クリニカルパスの作成
- 院内看護師対象の学習会の開催
※効果的に行うために、病棟毎に小人数による学習会とした。
※平均35%、約60人の参加があった。 - 糖尿病新聞の発行
7月、12月、2月に発行し、各病棟に配布 - 病院祭へ糖尿病チームとして参加
※パネル展示 ※血糖測定:約300名の血糖測定を行う。 - 糖尿病教室の開催:看護師担当は5週間に1回
※平均5~6名の参加
| 担当者 | 内容 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 医師 | 糖尿病について(正しい理解の為に) 合併症について(合併症を知る 合併症を防ぐ) |
計 485名 |
| 看護師 | 糖尿病患者のための日常生活の心得(感染症予防) よりよい血糖コントロール等10項目 |
|
| 薬剤師 | 糖尿病の薬について | |
| 管理栄養士 | 食事療法の基本・食品交換表の使い方・食事のヒント | |
| 健康運動指導士 | 運動療法(誰にでもできるやさしい運動) |
17.感染看護の取り組み
平成17年度前半は、病院機能評価を視野にいれ、処置室の水周りや汚染状況、汚物処理の実態などを中心に病棟ラウンドを行い、フィードバックしながら問題点を絞り対応を行った。その結果を基に後半期はゴミの分別に焦点を絞り検討した。2月にゴミ焼却処理場の視察を行い、病院として医療廃棄物に対する責任ある手順や行動を痛感した。次年度に向けて具体的な改善につなげる活動に結びつけたい。感染予防対策(主に手洗いの重要性について)については、委託業者やパートの補助員を対象に教育を行った。
主な活動内容については下記のとおりである。
| 活動月 | 活動内容 |
|---|---|
| 平成17年4月 | ・平成17年度活動目標・内容及び役割分担決定。 ・手洗いを中心とした新人及び転任者を対象とした感染予防教育 |
| 5月 | ・手洗いチェック表見直し ・病棟ラウンドチェック表作成(水周り及びゴミ分別など) ・ラウンド部署の計画表作成:4東西病棟ラウンド ※ラウンドの結果は部署毎に委員を通してフィードバックしていく |
| 6月 | ・救急センター及び各外来ラウンド ・小グループ活動によるIVH・ネブライザー器具の取扱い・環境整備・ 血液培養などのマニュアル作成 ・看護職・看護補助員対象に手洗い自己評価チェック実施 |
| 7月 | ・3東・ICU・透析室ラウンド ・速乾式手指消毒剤の推進 ・回診車、ワゴン車などの環境整備として除菌クリーナー使用の推進 ・全職員対象感染集合教育:「当院の手洗いの実態から」 |
| 9月 | ・ICT発足 |
| 10月 | ・5月~9月迄のラウンド評価及び項目の見直し ・後半のラウンドはゴミの分別状況調査を行う ・5階東西・6階東西ラウンド |
| 11月 | ・委託業者対象(清掃部門14名)に1回目手洗い実技指導(谷口、岡元) ・病院祭:手洗いコーナー(谷口、萩原、松本、日高、山本) (女性54名 男性14名 子供22名の計90名) |
| 12月 | ・病院機能評価を踏まえたゴミ分別のあり方や現状分析の実施 |
| 平成18年1月 | ・小グループ活動の最終確認作業、ゴミの分別表示について |
| 2月 | ・委託業者(清掃及びリネン18名)への2回目手洗い実技指導 ・感染性ゴミ処理場(中間、終末)2施設視察:都城 |
18.母性看護への取り組み
<院外>
1.思春期教育~命の大切さを考える
| 開催・日時 | 教育内容 | 対象 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 2006年2月 8日 5校時 | 性教育・命の大切さ | 細田中学校 | 48名 |
| 2006年2月15日 5校時 | 性教育・命の大切さ | 細田中学校 | 46名 |
| 2006年2月17日 6校時 | 性情報への対応 | 飫肥中学校 | 90名 |
| 2006年3月 9日 6校時 | 生命の誕生 | 吾田中学校 | 190名 20名(保護者) |
| 2006年3月10日 6校時 | 性非行、性犯罪 | 飫肥中学校 | 90名 |
*講演~助産師:門川久子・中倉輝子
2.おっぱい相談会
8月2日:宮崎(宮崎保健所)2名参加( 畑田 久美・小川 晶子 )
8月4日:都城(母子保健センター)2名参加( 後藤 朝美・蒲生 由佳 )
助産師職能・助産師会主催
3.まちの保健室相談会
6月25日:宮崎(宮崎カリーノ) 育児相談 (畑田 久美)
7月17日:宮崎(宮崎カリーノ) 育児相談 (畑田 久美)
平成18年1月15日 3回参加(畑田) 看護協会主催
<院内>
母親学級
- 中期:第3水曜日
対象:16週から
内容:妊娠中の心得・エクササイズ・ソフロロジー法について・栄養・他 - 後期:第4水曜日
対象:28週から
内容:分娩の準備・ソフロロジー・他
延べ参加者:中期(50名・夫3名) 後期(92名・夫2名・実母3名)
19. 臨床工学業務内容・取り組み
臨床工学技士は平成15年度から2名配属されている。OP室と透析室に配属され、OP室や透析室の医療機器の管理をはじめ、人工呼吸器をはじめとした様々な機器の中央管理、各種機器の整備を行っている。また病棟での部署別勉強会の開催、新規採用者へのオリエンテーションなどを通して積極的に啓発活動を行った。
活動の詳細は以下の通りである
| 月 | 実施事項 | |
|---|---|---|
| 4月 | 27日 | 自動血圧監視装置点検 手術室機器台帳管理 人工呼吸器バイパップビジョンマニュアル作成 年間目標立案 人工呼吸器勉強会:ME室にて5西新規採用者2名に実施 酸素濃度計点検・修繕 泌尿器科内視鏡システム点検 |
| 5月 | バイパップマスクの整備 | |
| 6月 | 15日 22日 | CHF勉強会:ME室にてICUの新人看護師11名に実施 人工呼吸器勉強会:講堂にて院内の希望した看護師50名に実施 超音波切開装置点検 4西保育器ME室管理とする |
| 7月 | 28日 | 気腹装置購入 人工呼吸器LTV/BiPAP取り扱い説明会:ME室にて看護師2名に実施 |
| 8月 | ICUサーボ300点検開始 中央材料室試験カード確認開始 RO水製造装置点検 | |
| 9月 | 人工呼吸器使用中点検開始 | |
| 10月 | PCPSオーバーホール(業者にて) 人工呼吸器エビタ4オーバーホール | |
| 11月 | パルスオキシメータ購入 テルモ輸液ポンプTE-112無償検査・点検処置施行(テルモと共に) | |
| 1月 | 人工呼吸器LTV災害用・搬送用へ変更 エアマット・患者監視装置テスト用治具購入 患者監視装置故障時点検開始 エンドトキシン吸着療法開始 無影灯点検 | |
| 2月 | 輸液ポンプ3台購入 低圧持続吸引点検治具購入・定期点検項目変更 内科外来除細動器故障にて新規購入 ME室環境整備・配置変更 | |
| 3月 | ICU血液ガス分析装置購入 検査室の使用済みECGをME室管理とする |
20. 平成17年度 中央材料室取り組みについて
| 平成17年4月7日 | 新人・転任者注意事項オリエンテーション「中材に関すること」施行 |
|---|---|
| 5月27・28日 | 第80回日本医科器械学会参加 |
| 6月 | アンビューバック洗浄を中材洗浄一元化 |
| 7月 | 中材リーダー業務を見直し文書化 |
| 7月9日 | 第6回ワークショップ「洗浄について」司会担当 宮崎病院 |
| 8月 | 年報に報告 |
| 8月22日 | 酸素マスク・チューブ・カニューラ・スキンステープラー・リムバー洗浄を中材洗浄一元化 |
| 9月14・26日 | 県立延岡病院中料より計6名見学受け入れ |
| 9月16日 | 院内感染勉強会で「中材の感染対策について」発表 |
| 9月21日 | 延岡医師会病院外来・中材師長より1名見学受け入れ |
| 9月 | ネブライザー蛇管洗浄を中材洗浄一元化 |
| 10月 | アミドブラック洗浄テスト学習会 |
| 11月7日 | 病棟ラウンド滅菌物チエック(蛇管ストック多い・ガーゼが棚の上にある) |
| 11月10日 | RO水を水の工事。チエック項目作成し3ヶ月現象調査 |
| 11月 | 全部署定数確認 |
| 11月 | 電子カルテに伴うオーダリングシステムから電子カルテへ |
| 平成18年1月15日 | 第38期 日本医療事務センター西部事業改善発表会で優秀賞獲得 |
| 1月27日 | 特定科学物質等作業主任者技能講習修了2名合格(EOG) |
| 1月28日 | 第15回宮崎医療材料滅菌・管理研究会にて山下発表 田中紙上発表 |
| 1月28日 | 院内看護研究中材から初めて発表(紙上) |
| 2月 | 普通第1種圧力容器取り扱い作業主任者技能講習修了1名合格 |
| 2月14日 | 宮崎大学附属病院より中材師長他2名中材見学受け入れ |
| 2月21日 | 院内TQM活動成果発表会 |
| 2月28日 | EOG環境テスト |
| 3月1日 | 看護補助員研修「中材に関するオリエンテーション」施行 |
| 3月14日 | 器材の写真付き洗浄基準化作成各部署へ配布 |
| 3月 | 病院運営会議にてRO水を水への切り替え承認 |
| 3月 | 人工呼吸器回路は各部署看護補助員が洗浄を中材洗浄一元化 |
| 3月20日 | TQMためしてガッテン隊 中央材料室の取り組みで最優秀賞獲得 |
| 3月27日 | 古賀総合病院より看護部長・手術室師長他計10名中材見学受け入れ |
平成17年度は、昨年の金属類だけでなく、酸素マスク等チューブ類・人工呼吸器回路の中材一元化を更に行なった。また看護補助員が全員新しいパート職員となったこともあり洗浄方法の標準化を図り器具器材の名前がわからないことへの対策として、写真付きの取り扱い説明書を配布した。
スタッフは改善発表会で2年連続表彰受け、宮崎県滅菌研究会でも委託職員では初めての発表を行なうことができた。3名の資格取得者が増えた。
当院中央材料室には、年間4施設、総数19名の見学者があった。
21.リエゾン精神看護への取組みについて
| 5月 | リエゾン精神看護、せん妄の予防・対処に対する1回目アンケートの実施 (対象:看護部、中材を除く全看護職員) |
|---|---|
| 7月 | 1回目学習会「リエゾン精神看護」「せん妄の予防」 (作成したパンフレットを用い、7月中に各部署別に昼のカンファレンスを 利用して小グループによる学習会とした) |
| 10月 | 「不安」・「暴力」・「徘徊」 3項目に関するNANDA標準看護計画を作成し、各部署に参考資料として配布 |
| 11月 | 事例検討会:11月18日 (家族看護に関連した2事例を提供し、参加者とグループワークを行う) (参加者:48名、アドバイザー:県立看護大教授 阿部先生) |
| 2回目学習会「せん妄の対処」「事例検討会での学び」 (作成したパンフレットを用い、11月中に各部署別に昼のカンファレンス を利用して小グループによる学習会とした) | |
| 11月 | 2回目アンケート実施(5月の1回目と同じ内容で実施し、比較検討した) |
- アンケートの結果で、学習会の理解度について各部署で差がみられたが、スタッフへのリエゾン精神看護に対する意識は高まったのではないかと思う。
- 事例検討会を通して、様々な「立場の変化」によりそれぞれの立場や気持ちを理解することが大切だということを再認識した。
22. 看護基準・手順改善への取り組みについて
今年度はおもに、作成月日のないものの見直しを行った。昨年度に続き、手順・基準の活用状況を調査したが、閲覧状況調査票の記入が100%ではない事があり、活用度については正確な資料とはなっていない。新人やたまにしかない処置・検査が行われる時にはよく活用されている。現在院内で施行していない検査については保留することとした。パスに関する資料はパス委員会が立ち上がった為、手順から外した。現在ファイルⅠ,2,3の3冊を使用しているが、手順Ⅲが特に多くなり増冊が必要となっている。このことについては次年度に検討することとした。
主な活動は以下のとおりである
- 看護基準の見直しと作成、目次改訂を行った
- 看護手順Ⅰの見直しと作成、目次改訂を行った
- 看護手順Ⅱの見直しと作成、目次改訂を行った
- 看護手順Ⅲの見直しと作成、目次改訂を行った
- 不要な手順に関しては削除を行った
23.看護記録向上への取り組みについて(記録推進委員活動から)
- 記録の充実を図り、看護の質の向上を目指す
- 電子カルテ導入に向けてのスムーズな運用ができる
上記目標達成のために毎月、第4木曜日に記録推進委員会を開催した。
主な活動は以下のとおりである
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 4月28日 | 平成17年度の目標、具体的目標について |
| 5月26日 | 記録に関しての質疑、意見交換 |
| 6月23日 | NANDAの看護診断マスターについての検討 転院サマリーの検討 |
| 7月28日 | NANDA看護診断のデーターベースの作成 クリニカルパス使用について |
| 9月22日 | 問題リストの記入方法についての検討 サマリー記入方法の検討 |
| 10月27日 | 電子カルテ導入に向けての準備についての話し合い |
| 11月24日 | 記録監査表の検討・・質・形式の監査表作成準備 |
| 12月22日 | 監査の基準の検討 |
| 1月26日 | 新監査表使用結果を話し合い |
| 2月23日 | 17年度目標の評価 |
| 3月23日 | 18年度委員会への要望、課題の話し合い |
24. 患者接遇向上への取り組みについて
目標
- 各自が接遇に対する意識を持ち実際の場で望ましい看護が提供できる
- 患者さんの声から満足度を知り対応できる
活動内容
- 「主に人権に関する留意事項」の表をもとに、各セクション毎に話し合いを行った。
- 4枚のポスターを作成、各セクションに提示し意識づけを行った。
「人柄は美しい言葉から」、「身だしなみ」、「笑顔」、「挨拶をしょう」 - 10月と2月の2回、接遇自己評価チエックを行った。
- 患者満足度アンケート調査の結果を各セクションで話し合い、患者の思いを知り改善策を検討した。
評価・課題
- 接遇研修が出来ず各セクションのカンファレンスでは各部署で話し合いの内容に差が出た。院内での接遇研修を行い接遇への意識レベルをアップさせる
- ポスターは見やすく意識づけに効果的であった。今後も継続する。
25. 看護科リスクマネジメント委員会の取り組みについて
平成17年度は新人・転任者のオリエンテ-ションを、担当者を決め、記録方法の演習も行なう事ができた。九州山口マネジメント学会・宮崎県看護協会での研究発表や、県TQM活動発表も行ない、当院の今までの活動状況や取組みを情報提供することができた。
報告システムの変更や集計方法の更新。部会への報告の際、優先した根拠を示す優先度検討シートを導入することができた。
| 時期 | 取り組み内容 |
|---|---|
| 4月7日 | 新人・転任者オリエンテーションをリスクマネジャーが施行 ①安全対策に関する院内独自の方法や目的を理解する (マニュアルに沿って・インシデント報告用紙の記入演習など) ②指さし呼称について ③与薬の傾向や注意点 ④記録について (書かなくてはならない記録、書いてはならない記録について)など |
| 5月 | 報告システムを変更したコピー看護科提出からファイルに綴じ提出方法へ |
| 5月 | 委員会・部会に優先度検討シートを導入し、集計方法を変更した |
| 6月17日 | 平成16年度分全部署集計・傾向の抽出 |
| 6月29日 | 院内インシデント報告会にて 看護科:4西 藤井主任発表 |
| 6月 | 案内カードの裏面に平面図を作成し配布、院内統一した |
| 7月 | 転落・転倒の男女比を調査。入院数の男女比に比例し有意差はなかった |
| 8月 | 日南病院年報に看護科リスクマネジメント委員会の取り組み報告 |
| 8月 | 病院長提案で「転落・転倒に注意しましょう」の院内掲示 |
| 9月 | 平成16年度の注射・薬間違い項目と発生件数調査 |
| 10月4日 | 地域連携室セミナー「インシデントのA・B・C」講演・地域の施設より 99名参加 講師:田中茂子中材師長 |
| 10月12日 | 「注射に関する取り決め」事項作成 |
| 10月30日 | 福岡(九大)にて医療マネジメント学会において 2演題発表(阪元・河野) |
| 11月1日 | 「つわぶき」作成メンバーがRM部会に参加することになった |
| 11月18日 | 「薬について」院内統一事項の検討会議 |
| 11月 | 機関誌「つわぶき」リスクマネジャー1名から5名で活動へ |
| 12月 | 内田明美主任医療安全管理者養成研修Ⅰ受講 |
| 1月 | 河野穂波主任医療安全管理者養成研修Ⅰ受講 |
| 2月22日 | 宮崎県TQM発表(中倉)2月17日宮崎県看護協会へ2演題申込み、採用となる (阪元・河野) |
| 3月11日 | リスクマネジャーへ4M4E学習会 |
| 3月16日 | 安全対策マニュアル一部改訂 |
| 3月18日 | 宮崎県看護協会にて2演題リスクマネジメント活動研究発表(阪元・河野) |
26. 看護師長による「健康相談室」の取り組みについて
看護科は、平成17年11月1日、「地域に開かれた、市民にとって身近な県立日南病院を実現し、併せて病院経営に寄与すること」を目的に、『健康相談室』を開設した。
相談件数は87件で、多くはないが、病気の診断・治療に関することから、看護・介護に関すること、クレームに関することまで様々な相談が寄せられ、キャリアを活かした対応を行うことで地域医療への貢献、また当院の医療や看護のアピールにもなっていると考えている。相談者からは「相談しに来てよかった」「聞いてもらって不満が解消した」「何でも相談できて安心感がある」といった評価がある。
相談内容は次の通りである
- 利用状況と相談内容:平成17年11月1日~平成18年3月31日
- 相談件数 : 87件
男性 : 35名
女性 : 52名
相談内容
| 区分 | 件数 | % |
|---|---|---|
| 病気の診断・治療 | 31 | 36 |
| その他 | 19 | 22 |
| 受診科の相談 | 12 | 14 |
| クレーム | 10 | 11 |
| コメディカル | 9 | 10 |
| 医療費に関すること | 4 | 5 |
| 看護・介護 | 2 | 2 |
| 合計 | 87 | 100 |
27. 看護師自治会の活動及び取り組みについて
専門職としての看護師の資質の向上に努めるため、また会員相互の親睦と福利を図ることを目的として活動している。今年度は自治会の組織をスリム化し、別枠であった教育委員を委員長も含めて自治会役員が兼ねることになった。毎年1回総会を開き、自主組織としての活動の質を図るために積極的に活動している。
今年度の活動は以下のとおりである。
| 内容 | 開催日 | 参加人数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 自治会総会 | 5/20 | 70名 | 講堂 |
| 事例検討会 | 6/18 | 29名 | 講堂 |
| NANDA勉強会① | 7/23 | 91名 | 講堂 |
| NANDA勉強会② | 8/6 | 102名 | 講堂 |
| 事例検討会 | 9/10 | 24名 | 講堂 |
| 集合教育 アロマでリラックス | 10/24 | 42名 | 講堂 |
| 事例検討会 | 11/5 | 25名 | 講堂 |
| 固定チームナーシング① | 12/10 | 91名 | 講堂 |
| 固定チームナーシング② | 12/11 | 67名 | 講堂 |
| 第35回看護研究発表会 | 1/28 | 95名 | 講堂 |
| 事例検討会 | 2/14 | 48名 | 講堂 |
| 看護の日 (院内でポスター掲示とミニタオル配布) | 5/12 | 15名 | 講堂 |
28. 電子カルテ導入への取り組み
平成16年度に策定された詳細設計に基づき、具体的な運用について各部門会議において協議を重ね、平成18年1月12日から3月3日にかけて各部門の操作研修を開始した。また、3月11日と3月25日、4月15日に模擬患者によるリハーサルを3回実施した。平成18年3月13日に「電子カルテシステム導入推進委員会」を開催し、①電子カルテの稼働日を平成18年5月1日とすること。②外来患者の呼び出し方法を姓名で呼び出すこと。③電子カルテ操作に係る権限委譲の考え方について決定した。
29. 地域がん拠点病院としての取り組み
圏域の住民が質の高いがん医療を受けることができる体制を整備するため、平成15年8月26日付けで、厚生労働大臣から「地域がん拠点病院」に指定された。
平成17年度は、委員会を3回開催し、取り組んだ業務内容は下記のとおり
- 入院症例についての全癌種の登録
- 院外講師による緩和ケア講演会の開催
- がん患者家族の心のケア、意見交換の場として院内施設を提供するがん患者家族の会を開催
- マンモグラフィー読影講習会の講習(外科医2名)
30. 診療情報管理室の活動について
平成17年度には、野辺千加(診療情報管理室)と切通秀子(看護師)の二人が診療情報管理士の資格を取得し、春山室長を加え診療情報管理士が3名体制となった。病名コーディング(ICD-10)の作業も精度と共に一段と充実したものとなり、データーベース作業も着実に進行している。
17年度の業務内容
- 退院患者のサマリー集計
病名コーディング(ICD-10)、
手術、処置コーディング(kコード、ICD-9-CM)
計結果は、毎月の代表者会議に報告 - 年報作成
入院患者疾病別統計(ICD-10)、死因統計、手術統計 - がん拠点病院として癌登録
- その他、診療情報検索システムの確立
31. 個人情報保護についての取り組みについて
個人情報保護法の施行に伴い日南病院も情報提供委員会を設置し、対策に取り組んだ。
- 院内に個人情報保護のお知らせを掲示した。(診療目的にだけ使用すること等)
- 電話での問い合わせにはいっさい答えないこととした。
- 見舞い客に対しては①番の入院案内窓口と時間外は守衛室のみの対応とした。
- 診療情報の提供に関しては、「県立病院における診療情報の提供に関する指針」に基づき「診療情報の提供に関する事務処理要領」を作成した。この要領により、医療連携科で「診療情報提供申出書」受付と事務処理を行っている。
17年度の申請件数は5件であった。
32. 3公立病院意見交換会について
平成16年7月から開始した3公立病院(中部病院、串間市民病院、県立日南病院)意見交換会は、平成17年度は8月3日(串間市民病院2階会議室)、平成18年3月3日(県立日南病院2階講堂)に開催した。当初は連携が主要議題であったが、本年度は入院患者の状況から経営改善に向けた方法などの具体的解決に向けた意見が多かった。
33. 女性専用外来「わかば」の開設について
平成17年10月21日から月1回、県内で2番目となる女性専用外来を開設した。更年期障害など女性特有の症状や悩みを気軽に相談できるよう専任の女性医師が対応することとしたもので、産婦人科外来隣の患者休憩ラウンジを改装し、第3金曜日午後1時から4時までの事前予約制で16歳以上の女性を対象としている。患者1人当たり最低30分以上の診察時間を確保し幅広く女性の体や心の悩みに応じることとした。
10月から3月までの利用者数は23名で、1日平均3.8名の利用状況である。
なお、「わかば」の名称は院内に幅広く募集し、多数応募のあったなかから当院のイメージに最もふさわしいとの理由で決定したものである。
34. 外来化学療法室の開設について
平成17年12月12日から、がん患者の安全性確保のため旧精神科診療室に外来化学療法室(ベット数6床)を開設した。設置目的は、免疫力の低下しているがん患者を一般患者と分離して治療することで安全性確保を図ること、投与時間中の患者負担の軽減を図ること、専用室を設置して化学療法を行うことで診療報酬上の加算点数が算定可能とすること等である。
業務内容は、与薬全般とその管理、診療は完全予約制で、外来通院が可能な化学療法の患者を対象としている。
管理責任者の室長は内科医長とし、薬剤師2名、看護師2名の専任職員を配置している。
35. 回復期リハビリテーション病棟設置検討委員会について
平成17年3月16日に調査、検討を目的とした回復期リハビリテーション病棟設置検討委員会規則を定め「委員会」を設置した。
平成17年6月8日に施設基準上の課題、患者数の予測を「第1回委員会」にて協議した。
平成17年6月27日、28日に現地調査(都城市の藤元早鈴病院、宮崎市の社会保険病院、潤和会記念病院)を行った。
平成17年9月13日に「第2回委員会」を開き回復期リハビリテーション病棟の設置検討を行ったが、現地調査の報告や対象患者数の確保の問題等さまざまな観点から検討した結果、本年度の設置は見送り今後引き続き検討していくこととした。
36. TQM活動
(1) 取組内容等
県立病院の診療機能の充実や患者サービスの改善等、病院事業の経営改善に向けて病院職員が自主的に調査研究する取組(TQM活動)に、当病院からも6チーム(63名)が参加し、特色あるテーマで活発な活動を行った。
また、平成18年2月22日には、各サークルが行ってきた活動を広く職員に知ってもらうことと、日南病院の代表選考会を兼ねて、院内でTQM活動成果発表会を開催した。
TQM活動のテーマ、チーム等は次のとおり。
- テーマ:「地域がん診療拠点病院の活動」
~緩和ケアチーム1年間の活動「家族会」から見えてきたもの~
チーム名:緩和ケアチームマーガレット
代表 看護科 主任看護師 福田雪子(構成員 7名)
活動内容:3人に1人ががん疾患と闘っている時代である。当院においても患者、 家族の緩和ケアをしていくために模索しており、その中で緩和ケアチームとして「家族会」を平成16年9月に立ち上げ患者・家族をサポートするための様々な活動や支援を行っている。 - テーマ:「楽しくバイキング」~しっかり選んでかしこく食べよう~
チーム名:食王(ショッキング)
代表 栄養管理科 主査 池田睦子構成員 16名)
活動内容:病院給食における患者サービスは、適時適温や選択食導入等段階的に向上しており、患者にとって食事時間は入院中の楽しみのひとつとなっている。入院生活に潤いを与えることと退院後の食生活のあり方を学んでもらうことを目的として病棟ごとに3回のバイキングを実施し、アンケートによる調査も行った。今後さらに給食サービスの向上と患者個々の栄養指導に取り組んで行きたい。 - テーマ:「看護科リスクマネジメント委員会の取り組みについて」
チーム名:災い転じて福となす
代表 看護科 副総看護師長 柿塚寿子(構成員 14名)
活動内容:より具体的な安全対策の質向上を目的に、特に危険度の高い注射や薬のインシデントの傾向を抽出し、統一した方法への取組みや報告書の提出やデータの集計システムの改善等に取組み効果が得られた。
また、学会発表等を行うことで看護科リスクマネジメント委員会の人的育成にも繋げることができた。 - テーマ:「中央材料室の取り組み」
~組織体制の充実・人材育成・業務改善を通じて~
チーム名:ためしてカイゼン隊
代表 中央材料室 看護師長 田中茂子(構成員 7名)
活動内容:安全やサービスを低下させることなく、質や効率化を目指して業務改善しているが、現状調査することや根拠に基づいた情報収集をすることで新たな改善や課題にも直面する。このため行ってきた改善を検証することで、課題や成果を明らかにし更なる業務改善や組織体制の充実・人材育成等に取り組み成果が図られた。 - テーマ:「バランスト・スコアカード導入による地域連携業務のブラッシュアップ」
チーム名:ぬっき~ず
代表 地域医療連携/医療相談室 医長 木佐貫 篤構成員 5名)
活動内容:地域医療連携/医療相談室(以下連携室)では、前方連携(紹介率アップなど)後方連携(退院調整など)に様々な取り組みを行い成果を得てきた。しかし地域医療連携業務の大半は非財務的な業務であることからその目標や成果を明確な指標として表わすことはできていない。
そこで企業ではすでに広く取り入れられており近年病院経営にも活用されつつあるバランスト・スコアカード(BSC)の考え方を連携室に導入して業務のブラッシュアップをはかることを目的としてTQM活動に取り組むこととした。具体的には地域連携業務の整理、連携室ビジョンの明確化、ビジョン達成のための戦略の具体化と目標設定を行う。これらの取り組みを通じて、病院の中での連携室業務の目標と成果、課題を明確にしていく。 - テーマ:「師長のキャリアをもっと活かそう」
~看護師長による「健康相談室」の開設~
チーム名:生き生き若葉輝き隊
代表 看護科 副総看護師長兼外来師長
山崎美鈴構成員11名)
活動内容:「外来待ち時間対策」の一つとして、「看護師長のキャリアを活かした、患者さんや家族の方々への『健康相談室』の開設」に取り組み、地域に開かれた、市民にとって身近な県立病院を実現し、併せて病院経営に寄与することを目的とする。平成17年11月から、平日の9時30分~11時30分の間エントランスホールにて各看護師長が交代で健康相談等を行うこととした。
(2) 県大会
平成18年3月20日に宮崎市で開催され、上記6チ-ムのうち、③・④・⑤の3チームが当院の代表として参加した。結果は④の「ためしてカイゼン隊」が最優秀賞に、⑤の「ぬっきーず」が優秀賞に輝いた。
TQM活動とは?
Total Quality Managementの略語で、もともとは企業の製品及びサービスの品質と競争力を向上させるため社会的レベルで行われる取り組み。
ここでは、県立病院の診療機能の充実や患者サービスの改善等、経営改善に向けて、職員の皆さんが自主的に調査研究することをTQM活動と呼んでいる
37. 病院だよりの発行状況
県立日南病院では、院内情報誌として「病院だより」を発行しているが、平成18年1月発行から 『南風(なんぷう)』と名称(職員から公募して決定した。)を変更してより充実した紙面づくりをめざしている。
平成17年度の発行状況は、次のとおり。
| 号数 | 発行日 | 掲載内容 |
|---|---|---|
| 38 | 17.6.11 | ・日南病院へ ウエルカム~病院のユートピアを目差して。 『わかば』より、『大樹へ』。(院長 柴田紘一郎) ・副院長昇任のごあいさつ(副院長 春山康久) ・転入者・新規採用職員の紹介 ・鏡視下手術のはなし(外科部長 峯 一彦) ・生化学自動搬送システムを更新しました臨床検査科技師長 籠 正利) ・お知らせ~初診にかかる特定療養費(787円)の徴収について 個人情報の取扱いにかかる窓口について ・救急受診についてのお願い ・おめでとうございます~院内顕彰 ・投書箱の意見 ・院内の出来事あれこれ ・広報編集委員の紹介 ・外来診療日程表 |
| 1 | 18.1.25 | ・「病院だより」から「なんぷう(南風)」へ (院長 柴田紘一郎) ・この人紹介 ボランティア活動 ・雑談 謝辞 抱負 (泌尿器科医長 新川 徹) ・みなさんのご意見コーナー ・医療連携コーナー「病診連携って何?」(地域医療連携/医療相談室) ・なんぷう雑感 (副院長 春山康久) ・平成17年のトピックス ☆初めてのバイキング ☆こどもスケッチ大会 ☆女性専用外来「わかば」オープン ☆「外来化学療法室」開設 ・賑わった第7回県立日南病院祭 ・外来診療日程表 |
| 2 | 18.3.31 | ・県立日南病院退職に寄せて(院長 柴田紘一郎) ・柴田紘一郎病院長にインタビュー ・小児の発熱と解熱剤 (小児科医師 高橋真悠子) ・看護科コーナー ~風は南(日南)から~(総看護師長 野口初代) ・平成17年度患者満足度調査について (患者サービス検討部会) ・ためになる話 ~快適な睡眠の工夫等~ ・5月1日から電子カルテを導入します (電子カルテシステム整備担当) ・外来診療日程表 |
38. 職員情報誌「スマイル通信」の発行について
県立日南病院では、職員向けに各部署ごとに情報誌(連携室だよりやお薬かわら版、臨床工学士だより等)を発行していたが、平成17年8月から、一つにまとめて、定期的に毎月最終金曜日に発行していくこととしし、名称は職員から応募のあった『スマイル通信』に決定した。「接遇(応対)の基本は笑顔(スマイル)である。いつでもどこでも笑顔で応対しよう。」という思いで、病院の情報が周知・共有化され、改善・活性化につながるような情報誌づくりをめざしている。
平成17年度の発行状況等は、次のとおり。
| 号数 | 発行日 | 掲載内容 |
|---|---|---|
| №1~8 | 17.8.26 創刊 18.3.31 まで | ・院内ニュースあれこれ ・連携室だより ・お薬かわら版 ・リスク発 つわぶき ・CE(臨床工学士)通信 |
39. 県立日南病院の研究支援ネットワークについて
当病院は、インターネットを通じて研究支援ネットワークを構築している。
インターネットへは現在宮崎情報ハイウェイ21の光ケーブルを利用し、30~50M6PSのスピードで常時接続している。
インターネットと病院内の研究支援LANの間には、ファイヤーウォールを設置して不正アクセスに備えている。
国内外文献検索のためには、独立行政法人科学技術振興機構と契約してインターネットによる科学技術文献情報データベース「J Dream」による迅速な情報検索体制を整えている
40. 県立日南病院ホームページについて
平成17年8月、ホームページをトップページから完全リニューアルした。
親しみやすいホームページをめざし、従来の診療科の紹介だけでなく看護科・薬剤科・放射線科等各部門のページも加えて内容の充実を図った。 併せて、新着情報や行事案内、お知らせ欄等情報のより迅速な更新を行っている。
41. 南睦会活動状況
職員の親睦を図るため「南睦会」を組織しており、各種レクリェーション、交流会、職員及び家族が参加する文化祭等を開催し、売店の運営等の事業を展開している。
平成17年度の「南睦会」の開催行事は、次のとおり。
| 年月日 | 行事 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 17.11.27 | 文化祭(職員・家族) | 日南病院第2会議室 | 病院祭に合わせて |
| 17.12.16 | 交流会 | ホテルシーズン日南 |
この他に、硬式テニス他の運動部、華道他の文化部、南那珂地区球技大会、全管球技大会、県立病院職員レクレーション大会等の助成を行っている。







